| |
自然の摂理から生まれた学問である日本古学を「清風道人(せいふうどうじん)」が現代と未来に伝えていきます。
日本古学から学ぶ「自然の摂理」と「日本古来の精神」が次の豊かで健やかな世界を創るヒントとなることを願って。
会員登録をいただくと、タイトルに●の付いている会員様専用の記事閲覧と、
「清風道人(せいふうどうじん)」への質問欄『Q&A(会員様のみ)』のご利用と過去の質問および回答を閲覧いただけます。
更新情報メールの配信をご利用頂けます。
会員登録はこちらから>> カードでのお申し込み 銀行振込でのお申し込み |
 |
|
|
 |
#00199 2012.10.31
清明伝(2) -心の祓い清め-
●
|
|
禊ぎ祓えの神術は、清らかな水によって身体を祓い清める道術ですが、古神道ではその際の方法が詳しく伝えられており、またそれ以外にも邪気を払拭する神法道術が数多く伝承されています。これらの神術によって身体だけでなく心も清まることは、須佐之男命の罪の解除の後の、天照大御神に対する言葉を見てもよくわかります。 #0083【災い転じて福となる
|
|
|
カテゴリ:清明伝 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
#00198 2012.10.25
清明伝(1) -災いは穢れから-
|
「畏(かしこ)くも神代(かみよ)の昔、伊邪那岐命の黄泉(よみ)の穢れに交じり給ひしより初めて妖神邪気世に出現し、天下の人民をして正道を誤らしめ、悪人に福し善人に禍して世界を擾乱(じょうらん)せむとし、また人の私欲を進めて正心を昏(くら)まし、その人の私心に乗りて悪欲を長ぜしめるに至る。」
これは明治の謫仙(たくせん)宮地水位先生の手記の一�
|
|
|
カテゴリ:清明伝 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
#00197 2012.10.19
神道講話(4) -愛国のこと-
●
|
この話は、宮地厳夫先生(宮内省式部掌典として明治天皇の側近を務められた明治における神道界の重鎮)が、極めて通俗的に一般の方を対象として神の道を説かれたものです。(現代語訳:清風道人)
国土(地球)は、天神(あまつかみ)様が御経営なされて我ら人間が繁殖して生息すべき地と御定めなされ、またその天神様の御正統とまします我が皇上(てんし)様を御�
|
|
|
カテゴリ:神道講話 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
#00196 2012.10.13
神道講話(3) -尊皇のこと-
●
|
この話は、宮地厳夫先生(宮内省式部掌典として明治天皇の側近を務められた明治における神道界の重鎮)が、極めて通俗的に一般の方を対象として神の道を説かれたものです。(現代語訳:清風道人)
皇上(てんし)様は、天神(あまつかみ)様の御手に代わってこの天下を統(す)べ治(し)ろしめす御方様で在らせられますので、天神様と御同様に尊び奉らねばなりま�
|
|
|
カテゴリ:神道講話 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
#00195 2012.10.6
神道講話(2) -敬神のこと-
●
|
この話は、宮地厳夫先生(宮内省式部掌典として明治天皇の側近を務められた明治における神道界の重鎮)が、極めて通俗的に一般の方を対象として神の道を説かれたものです。(現代語訳:清風道人)
神様とは、いかなる御方を申し上げ奉るのでありましょうか。まずよくこれを知るのが第一のことでありますが、その神様のことを知ろうと致すには、この天地世界の上を�
|
|
|
カテゴリ:神道講話 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
#00194 2012.10.1
神道講話(1) -人間に与えられた天命-
|
この話は、宮地厳夫先生(宮内省式部掌典として明治天皇の側近を務められた明治における神道界の重鎮)が、極めて通俗的に一般の方を対象として神の道を説かれたものです。(現代語訳:清風道人)
神様は何のためにこの天地万物を御造化(おつくり)なされたのでありましょうか。また、人間は何のためにこの世界に生まれて来たのでありましょうか。この訳を知るこ�
|
|
|
カテゴリ:神道講話 |
続きを読む>>
|
|
|
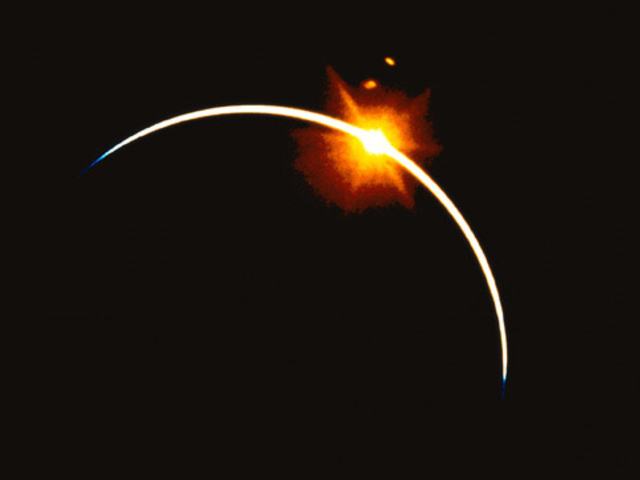
|
|
 |
#00193 2012.9.25
『古事記序文』解説(5)
●
|
|
「伏して惟(おも)ふに、皇帝陛下、一を得て光宅(こうたく)し、三に通じて亭育(ていいく)したまふ。紫宸(ししん)に御(ぎょ)して徳は馬蹄(ばてい)の極むる所に被り、玄巵(げんし)に坐(ま)して化は船頭の逮(およ)ぶ所を照らしたまふ。日浮かびて喗(ひかり)を重ね、雲散りて烟(けむり)に非ず。柯(えだ)を連ね穂を幷(あわ)すの瑞史(しるし)、書する�
|
|
|
カテゴリ:日本の神伝 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
#00192 2012.9.19
『古事記序文』解説(4)
|
|
「ここに天皇(すめらみこと)詔(の)りたまはく、「朕(われ)聞く、諸家の賷(も)てる帝記及び本辞、既に正実に違(たが)ひ、多く虚偽を加ふと。今の時に當(あ)たりてその失(あやまり)を改めずは、未だ幾年(いくとせ)を経ずしてその旨(むね)滅びなむとす。これ乃(すなわ)ち邦家の経緯、王化の鴻基(こうき)なり。かれ、これ帝記を撰録し、旧辞を討覈(とう�
|
|
|
カテゴリ:日本の神伝 |
続きを読む>>
|
|
|
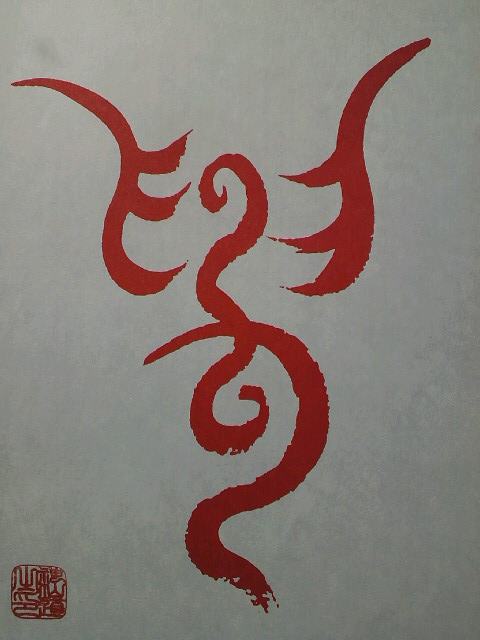
|
|
 |
#00191 2012.9.13
『古事記序文』解説(3)
●
|
「飛鳥(あすか)の清原(きよみはら)の大宮に、大八洲(おおやしま)御(しろしめ)しし天皇(すめらみこと)の御世に曁(およ)びて、潜龍(せんりゅう)元を体し、洊雷(せんらい)期に応ず。夢の歌(みうた)を聞きて業(わざ)を纂(つ)がむことを想ひ、夜の水に投(いた)りて基(もとい)を承(う)けむことを知ろしめす。」
(現代語訳:清風道人)
「飛鳥�
|
|
|
カテゴリ:日本の神伝 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |