| |
|
 |
#00527 2018.04.1
扶桑皇典(57) -人は長寿ならざる可らず-
●
|
人生は、長寿ならざる可らず。長寿ならざれば、一家団欒も、富貴栄達の慶も来(きた)る可らず。然れば、一家団欒の楽、富貴栄達の慶を思はん人は、まず長寿より求めざる可らず。
長寿を求めんとするには、必ず人身を知らざる可らず。人身は父母より受くるにはあれども、人身に舍(やど)れる主宰の神魂(たましい)は、皇産霊神(みむすびのかみ)の賦与し給へる物に
|
|
|
カテゴリ:扶桑皇典 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
#00526 2018.3.26
扶桑皇典(56) -先祖祭-
●
|
天神地祇を敬ふと、祖先を崇むるとは、同じ心ばへなれば、醍醐天皇は、式内の神社、また他の古社の、所在地の不明に為りたるを尋ねさせ給ふ傍には、官符を以て、「諸人の家々にて行ふべき二月、四月、十一月の氏神の霊祭を怠る可らず」と宣(のたま)ひたり。これ、国民は総て供奉(ぐぶ)の神の子孫にて、その祖先を祀る、即ち諸神を祭ると一般なればなり。
然る�
|
|
|
カテゴリ:扶桑皇典 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
|
|
 |
#00524 2018.3.14
扶桑皇典(54) -武事の神-
|
|
武事を掌り給ふ大神は、武甕雷神(たけみかづちのかみ)・経津主神(ふつぬしのかみ)と申す。この大神たちは、伊邪那岐命の、火産霊神(ほむすびのかみ)を斬り給ひし時に、その御刀(みはかし)に因りて生(な)り出で給ひし大神にて、その宮は、武御雷神は常陸国鹿島郡にて、鹿島神宮と申し、経津主神は下総(しもうさ)国香取郡にて、香取神宮と申せり。 |
|
カテゴリ:扶桑皇典 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
#00523 2017.3.8
扶桑皇典(53) -海の神-
●
|
海の神は、大綿津見神(おおわたつみのかみ)と申す。伊邪那岐命の御身滌の時に生(あ)れ出で給ひし大神にて、河海大小の神を総管し給へり。 #0061【祓戸四柱神の誕生】>>
この大神の御社は、筑前国糟谷郡志加に坐して、海(わたの)神社三座と申す。猶、この海神(わたつみのかみ)の御社は諸国に在り。
俗には海神の宮を龍宮と称へるが
|
|
|
カテゴリ:扶桑皇典 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
#00522 2018.3.2
扶桑皇典(52) -山の神-
●
|
山神は、大山津見神(おおやまつみのかみ)と申す。この神は、迦具土神(かぐつちのかみ)の御体より化(な)り給ひし大神にて、諸国諸山を守り給ふ、総ての山神たちを管領し給へり(『八十能隈手(やそのくまで)』。 #0055【神々の分体と合体】>>
山神の、山を守り給ふは、山の草木のみにはあらず。山に棲む獣類をも守り、また管領し給ふが�
|
|
|
カテゴリ:扶桑皇典 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
#00518 2018.2.7
扶桑皇典(48) -風の神-
●
|
風は天地の間の気にて、万物、皆これを呼吸して活けるは言ふも更にて、人の物言ふ声の遠きに聞こゆるも、またこの風の力なり。
往昔、坂東の子女、瘧病(わらわやみ)に患ひて、臨終の時、母を恋ひて、三度母を呼びて亡(う)せたるに、その声、一日路(ついたちみち)を隔てたる地に居(おり)たる母の耳に、分明に聞こえたりといへり(『雑談集』)。
前にい�
|
|
|
カテゴリ:扶桑皇典 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
#00517 2018.2.1
扶桑皇典(47) -衣食住の神-
●
|
衣食住は、人生の大事中の大事なるに、別(わ)きて穀物は、一日も欠く事能(あた)はざる物なれば、人類の危惧騒動も、多くはこの物の欠乏よりして起こる事なり。
さて、この五穀を掌り給ふ大神は、豊宇気姫神(とようけひめのかみ)と申し、また宇迦之御魂命(うかのみたまのみこと)とも、保食神(うけもちのかみ)とも申せり。 #0073【鳥獣魚�
|
|
|
カテゴリ:扶桑皇典 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
#00516 2018.1.26
扶桑皇典(46) -神の御分業-
●
|
天神地祇は八百万(やおよろず)坐せど、皆掌り給ふ所ありて、一様の御事にはあらず。山神は山を知食(しろしめ)して人間を守り給ひ、海神は海を知食して人間を守り給ふ。火神の火を知食し、水神の水を知食すも同じ。
然れば、その知食す事同じからねば、一柱の神にして難事を兼併(けんぺい)し給ふといふ事は、殆ど稀なるべし。
然れども、人はその神の掌り�
|
|
|
カテゴリ:扶桑皇典 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
|
|
 |
#00514 2018.1.14
扶桑皇典(44) -神に習ふべし・下-
|
|
また、神たちは孝心深くおはしまして、よく御祖(みおや)の神を斎(いわ)ひ給へり。天照大神は、御父神・伊邪那岐命の賜ひし八尺(やさか)の勾玉を御棚上に居(す)ゑさせ給ひて、御倉棚神(みくらたなのかみ)として祀らせ給ひしは、御孝心の程さへ見えて、畏(かしこ)しとも畏し。然れば、先輩の説に、今、人家に神棚といふがあるも、この御倉棚に倣ひ奉りたるには�
|
|
|
カテゴリ:扶桑皇典 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
#00513 2018.1.8
扶桑皇典(43) -神に習ふべし・上-
●
|
神代の時、春山之霞壮士(はるやまのかすみおとこ)は、秋山之下氷壮士(あきやまのしたひおとこ)の、約束の物を与へざりしを恨みて、御母の神に訴へしに、母神は「我が御世の事、よくこそ神習はめ、顕(うつ)しき青人草、習へや、その物償はぬ」と咎め給ひし事あり。
この御母の神の御言は、「神習の教」とて、今も常に言ふ事にて、上代は特に詔勅(しょうちょく)
|
|
|
カテゴリ:扶桑皇典 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
#00510 2017.12.21
扶桑皇典(40) -禁厭-
●
|
|
禁厭(まじない)は一種の神法にして、人その法を行へば、法の上に神霊降下して効験を現すなり。然れば、その範囲も広大にして、こゝに一言にて尽くし難しと雖(いえど)も、その一班を約言すれば、神代に天神の、天上の水を濯(そそ)ぎて大八洲国の水を真清水に為し給ひしも禁厭なり。天孫の降臨に際し、稲穂を以て霧を拂はせ給ひしも禁厭なり。 #
|
|
|
カテゴリ:扶桑皇典 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
#00507 2017.12.2
扶桑皇典(37) -妖獣-
●
|
猫もまた妖を為す物にて、その人語を為し、踊りを躍るなどいふ事は、普く人の知れる事なれど、死人を動かすは珍しければ、こゝにその一話をいふべし。
下総(しもうさ)国小金といふ地の辺りに栗澤村といふありて、その村に、独り者の老婆の亡(う)せしかば、近隣の人集まりて、野辺送りの事など語り合ひて在りしに、夏の暑中の事なれば、諸人、戸外に出でゝ涼み�
|
|
|
カテゴリ:扶桑皇典 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
|
|
 |
#00505 2017.11.20
扶桑皇典(35) -妖物-
●
|
|
幽界には、また魔といふ物あり。魔は鬼物にて、人を恐怖せしめ、或はその業を妨ぐるなどの事をする物なり。この物は皆外国より来る物か、かの稲生平太郎を三十日間も悩ましたる山本(さんもと)五郎左衛門といふ魔王は、その詞(ことば)に、「我が日本に来りしは源平合戦の頃なり。我が類の魔王にては、日本にては今一人、神野(じんの)悪五郎といふ者あり」といへり。�
|
|
|
カテゴリ:扶桑皇典 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
#00504 2017.11.13
扶桑皇典(34) -霊人-
|
幽界には高貴なる神も坐せど、また卑賤なる神もあり。正神・善神も坐せど、また邪神・悪神も居(お)れば、正神・善神の正事・善事に幸(さきは)ひ給ふ傍らには、邪神・悪神は邪事・悪事を勧めて、邪道に誘(いざな)ふ事もあるべし。
然れど、正神・善神は申すも更なり、邪神・悪神も、その心の和める時には、然る事も無くてあるべし。然れば、神には禍津日神(まが
|
|
|
カテゴリ:扶桑皇典 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
#00503 2017.11.7
扶桑皇典(33) -亡霊・下-
●
|
亡霊は神の如くにて、顕界の人と異なれば、亡霊に追はるゝ時は、隠るゝ事を得ず。
慶長年中、京に成田治左衛門といふ人ありて、夫婦の間も睦じかりしを、妻病みて死なんとする程に、夫の手を取りて、涙ながらに言ふやう、「形は煙と為らばなれ、魂魄(たましい)は永く御身の傍を離れん」といひて、終に空しく為りしに、死後、数日を経てより毎夜、治左衛門の枕頭に来
|
|
|
カテゴリ:扶桑皇典 |
続きを読む>>
|
|
|
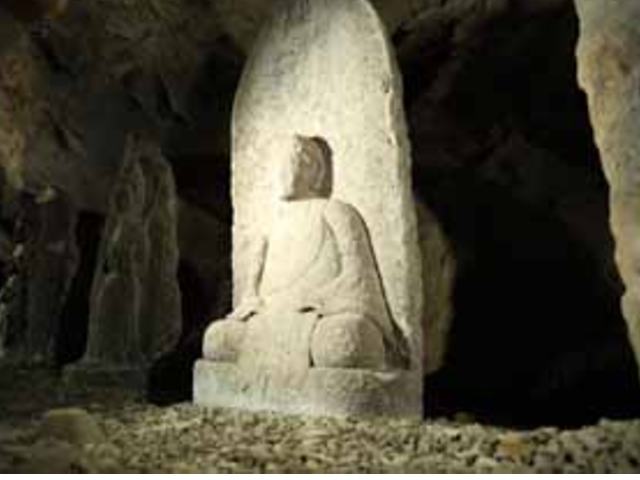
|
|
 |
#00502 2017.11.1
扶桑皇典(32) -亡霊・上-
●
|
死後の神魂(たましい)は全く神の如くなれば、人智を以ては知られざる奇異なる動作もありて、一例をいへば、他の体を借りて自己の物とし、或は生ける人を数百里外に誘(いざな)ひ、或は瞬間に水陸を隔てたる夫の許に赴き、或は人にも祟り、人をも殺す事あり。
その、他の体を借りしは、越後の新潟に長尾何某(なにがし)といふ医者ありしが、この人、若年の頃、�
|
|
|
カテゴリ:扶桑皇典 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
#00499 2017.10.14
扶桑皇典(29) -死-
●
|
死とは、人身に舍(やど)れる神魂(たましい)の離れ去るをいふ。更にいへば、人身の、神魂を失ふをいふ。この死は、識者にも惑へるがあれば、凡俗は何の知る所も無くてあれど、何人(なんびと)も逃るゝ事を得ねば、その消息は極めたる大事にして、予(かね)て心得おくべき第一の要事なり。
越後国魚路(うおじ)の南方に猿峠といふ地ありて、そこに才三郎とい�
|
|
|
カテゴリ:扶桑皇典 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
#00492 2017.9.1
扶桑皇典(22) -卜占-
●
|
卜占(うらない)は、また宇良登比(うらとい)ともいふ。神の心を問ふ義にて、自己の心に思ひ定め難き事のある時に、神に問ひてその教へを請ふ事なり。
然れば、その事を擬(なぞら)ふには、大小軽重に関らず、予(かね)て定め置きたる事物に現るゝ兆(きざし)を見て、神慮なりとして、その吉凶を決する事なれば、本邦に限らず、世界万国にて行ふ事にて、その作法
|
|
|
カテゴリ:扶桑皇典 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
#00491 2017.8.26
扶桑皇典(21) -神憑-
●
|
神憑(かみがかり)は、本邦にては古来、常に聞こゆる事なるが、これもまた神国の一異事にて、外国には多く聞こえず。本邦にては、神代にも既に聞こえて、天細女命(あめのうずめのみこと)は磐屋戸の御前にて神憑したりといへり。 #0080【神楽の起源】>>
また、この神憑の、祝部(はふりべ)にあるは然る事なるを、然らぬ人にも憑り給ふ事あり�
|
|
|
カテゴリ:扶桑皇典 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
|
|
 |
#00489 2017.8.14
扶桑皇典(19) -神の恵・下-
●
|
|
一条天皇の御時、赤染衛門(あかぞめえもん)といふ女房は、子の挙周(たかちか)といふが重く患ひけるを嘆きて、住吉明神に参籠して、「この母の身に代へて、子の命を助けさせ給へ」とて、祈願を凝らして御幣(みてぐら)を奉りける時、御幣の串に一首の歌を書き付けて、「代はらんと命は惜しからでさても別れん事ぞ悲しき」と詠みて奉りし程に、神も納受や為させ給ひに�
|
|
|
カテゴリ:扶桑皇典 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
#00488 2017.8.8
扶桑皇典(18) -神の恵・上-
●
|
神たちの、世を守り、人を恵み給ふは、言ふも更なる事なれど、隠岐国知夫(ちぶ)郡に坐す神は、商人などの船の、闇夜に海上に漂へるがある時は、必ず遠く火光(かこう)を現し、海上を照らして方角を示し給ふ事ありて、世にその神を「焼火(たくひ)権現」と称へ申せりといふ(『諸国里人談』)。
桓武天皇の延暦十八年の遣外国使の船も、帰路、海上に迷ひたりしを、
|
|
|
カテゴリ:扶桑皇典 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
|
|
 |
#00486 2017.7.26
扶桑皇典(16) -産土神及び氏神・上-
|
産土神とは、尾張の盧入姫(いおきのいりひめ)の誕生地の神社を宇夫須那(うぶすな)社といへるが如く(『尾張国風土記』)、その人の生まれたる地の神にて、即ち鎮守神を申せり。
然れば、産土神は、その地勢・方角に従ひて、その霊も異なる故に、産物にも異なる物あり、人物にも容貌・言語・心志・気性などの同じからぬもあり。
出雲国島根郡神埼の窟中(く�
|
|
|
カテゴリ:扶桑皇典 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
#00485 2017.7.20
扶桑皇典(15) -諸神-
●
|
|
諸神たちは、御壮容、万古不変におはしまして、御身には光明を湛へて坐すなるべし。神の御上を申さんは、畏(かしこ)しとも畏けれど、天照大御神の御光明は、天地の間を照らし給へりと申し、月読尊、素戔嗚尊の御光明も、天照大御神に次て坐せりと申し、味鉏高日子根神(あじすきたかひこねのかみ)の御光明は、二丘二谷の間に映じたりと申し、大国主神の和魂(にぎみた�
|
|
|
カテゴリ:扶桑皇典 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
#00482 2017.7.1
扶桑皇典(12) -幽政の神廷・中-
●
|
|
さて、神は人に対しては、かく種々の事も為(せ)らるれども、人は神に対しては、祈願と卜占(ぼくせん)とのみなれば、全く神の御事は知る事能(あた)はず。然れども、人も皇産霊神の霊徳に依り、産土神の神慮に依りて生まれ来(きた)る者なれば、上下尊卑の品こそあらめ、人もまた神なり。唯、その顕界に属せる肉身に舍(やど)れる為に、幽界を見る事能はざるなり。�
|
|
|
カテゴリ:扶桑皇典 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
|
|
 |
#00480 2017.6.19
扶桑皇典(10) -顕幽分界-
|
|
神代といふを、人ならぬ神の時代と思へるもあり、唯、何となき上代の事と思へるもあり、また朝鮮の太古の称ならんと思へるもあり、高天原の事ならんと思へるもあるは、神代といふ事、日本にのみ有りて、外国の歴史に無ければにて、その神の時代と思へるは、神の御事の多く見えたるが為にて、唯、上代の事と思へるは、外国の上古史にも不可思議なる記事ありて、神または神�
|
|
|
カテゴリ:扶桑皇典 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
#00479 2017.6.13
扶桑皇典(9) -天孫の降臨・下-
●
|
|
瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)は、笠狭(かささ)の御碕(みさき)におはせる間(ほど)に、大山祇神(おおやまづみのかみ)の御女(みむすめ)・木花開耶姫命(このはなさくやひめのみこと)と申す姫神を御后として、火須勢理命(ほすせりのみこと)・火遠理命(ほおりのみこと)と申す二柱の御子を生ませ給ひしに、火須勢理命は海幸彦として、自ら海の物を獲給ふ幸おはし�
|
|
|
カテゴリ:扶桑皇典 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
#00478 2017.6.7
扶桑皇典(8) -天孫の降臨・中-
●
|
|
高皇産霊神・天照大御神は、大国主神の、この御国を天孫・瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)に奉り給ひしからに、瓊瓊杵尊を葦原中国(あしはらのなかつくに)に降し坐さんと為させ給ひて、天照大御神は、三種(みくさ)の神器(かむたから)を瓊瓊杵尊に賜ひ、殊に神鏡を賜ふ時には、宝祚(ほうそ)の無窮を宣(のたま)はせ、高皇産霊神は供奉(ぐぶ)の諸神の棟梁たる天児屋�
|
|
|
カテゴリ:扶桑皇典 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
|
|
 |
#00476 2017.5.25
扶桑皇典(6) -諸神の御国造-
●
|
顕宗天皇の御代三年といふに、日神・月神は、阿閉臣事代(あえのおみことしろ)といふ人に憑(か)からせ給ひて、「吾が御祖(みおや)高皇産霊神は、天地鎔造の御功あり」と宣(のたま)ひて、神地を献(たてまつ)らせ給ひし事あり。
然れば、後に諸神たちの、尚、国土を造り給ひしを思ふに、大己貴神たちをはじめて、諸神たちは、外国もあれど、主(むね)とこ�
|
|
|
カテゴリ:扶桑皇典 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
|
|
 |
#00474 2017.5.13
扶桑皇典(4) -天地開闢・中-
●
|
|
伊邪那岐・伊邪那美二柱の大神は、国土、神人、万物を生み給ひての後、伊邪那岐大神は、伊邪那美大神の、火神・迦具土神を生み給ひしに依りて、御身労(わずら)はせ給ひて、黄泉国に出でましゝを嘆かせ給ひて、御跡を追ひて黄泉国に出でまして、図らずもその国の穢れに触れさせ給ひしかば、驚きて逃げ出で給ひて、伊邪那美大神の追ひ来ませるをも顧み給はずて、千引(ち�
|
|
|
カテゴリ:扶桑皇典 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
#00473 2017.5.7
扶桑皇典(3) -天地開闢・上-
|
天地の開闢を説かんとするに、世の学者は理論を以て推定せんとして、「太陽は一大火集なり、火雲の凝集せるなり。大地は岩球、岩層の二大部分を以て説くべし。月と星とは、その質、地球と同じくして、共に太陽の光輝を受けて耀くなり」と論ずれども、これは物ありて後の論にして、一物無き代の論にはあらず。
然れば、開闢の時の如き、未だ一物も無き時の事は、そ�
|
|
|
カテゴリ:扶桑皇典 |
続きを読む>>
|
|
|
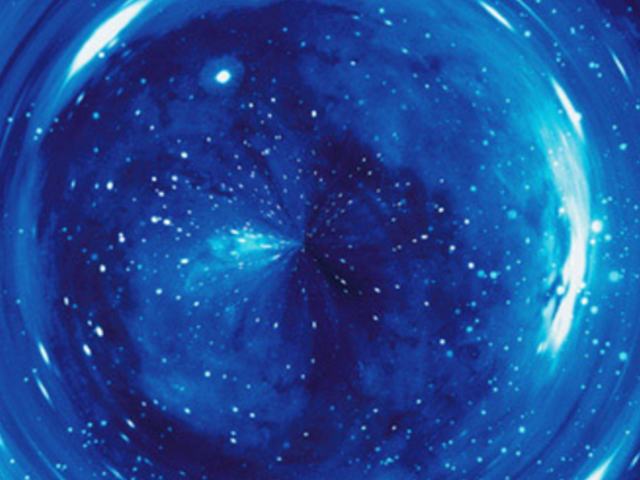
|
|
 |
#00472 2017.5.1
扶桑皇典(2) -人世-
●
|
|
人世は、人事・神事(幽事)相依り相随ひて、糾(あざな)へる縄の如く、吉凶禍福、纏綿(てんめん)して、輪の端無きが如くなれど、人こそ知らね、人世に発生する種々の事は、皆、神の幽契に依る事なれば、人事を論ぜんには、須(すべか)らく、まずこの神事より知らざる可らず。然(しか)れども、神事を知らんとするには、天地の間には人界の外に神界(幽界)ありて、�
|
|
|
カテゴリ:扶桑皇典 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
#00471 2017.4.25
扶桑皇典(1) -人智の狭隘-
|
|
(清風道人云、この『扶桑皇典』は、明治三年に平田鉄胤先哲の許に入門して古学を学び、更に漢学や洋学も修めた後、帝国大学や東京師範学校の教授等を歴任された文学博士・物集高見(もずめたかみ)先生が著された、幽界の実在を立証する格好の文献といえます。世には博士や大学教授といった肩書や地位に縛られて、内心秘かに幽界や霊物の存在を認めつゝも、これを口にし得�
|
|
|
カテゴリ:扶桑皇典 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |