| |
以前の記事 : 2016年9月
|
 |
#00437 2016.9.29
『本朝神仙記伝』の研究(55) -山門玄常-
●
|
山門玄常(やまかどげんじょう)は、その父母及び何処(いずこ)の人と云ふことを知らず。播磨国播磨郡雪彦山(せっぴこさん)に移り住む。雪彦山は姫路の西南三里ばかりにあり。
玄常は紙楮木(かみおぎ)の皮を以て衣に充(あ)つ。雨降り日照れども笠を著(き)ず。遠く遊ぶと雖(いえど)も草鞋(わらじ)を著(つ)けず。斎(ものいみ)を保ちて欠かさず、或�
|
|
|
カテゴリ:『本朝神仙記伝』の研究 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
#00436 2016.9.23
『本朝神仙記伝』の研究(54) -虚庵-
●
|
虚庵(きょあん)はその姓氏を知らず、またその生国を詳らかにせず。始め信濃国諏訪に住す。書画をよくし、最も篆刻(てんこく、印章の作成)に妙なり。且つ鷹を養ふの法に委(くわ)しくして、またよく鷹を描けり。
時に諏訪・因幡守家(いなばのかみけ)に悪臣ありて、主人を毒害せんと謀りしことのありし際にも、虚庵、独身(ひとりみ)にて密かに江戸に至り、執政
|
|
|
カテゴリ:『本朝神仙記伝』の研究 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
#00435 2016.9.17
『本朝神仙記伝』の研究(53) -髭道人-
●
|
髭道人(ひげどうじん)は姓名及び生国(しょうごく)を知らず、故に何人(なんびと)たるを詳らかにせず。
大和国下市村に中山何某と云ふ人あり。癸(みずのと)未(ひつじ)年十月、一人の道人あり、下市に至り、街中の諸家に入りて銭を乞ふ。歳八十有余に見ゆ。長き髭は雪の如くにして胸に垂れ、眼光は稲妻の如くして人を射る。時既に初冬にして、寒風肌を襲ふと雖
|
|
|
カテゴリ:『本朝神仙記伝』の研究 |
続きを読む>>
|
|
|
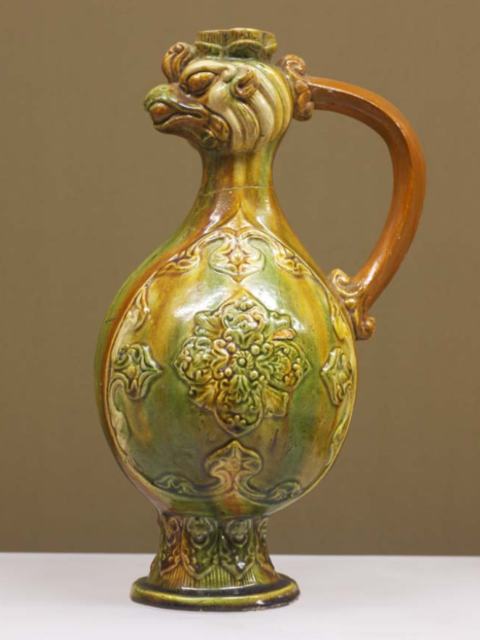
|
|
 |
#00434 2016.9.11
『本朝神仙記伝』の研究(52) -於竹女仙・於松女仙-
|
於竹(おたけ)女仙は、世に於竹大日如来と称す。何処(いずこ)の産(うまれ)にて何人(なんびと)の女(むすめ)なることを詳らかにせず。故にその姓氏もまた知るに由(よし)無し。
明正(めいしょう)天皇の寛永年間のことゝか、江戸の大伝馬町に佐久間勘解由(かげゆ)と云へる豪家あり。於竹は元この家の卑女(はしため)なりしが、天性慈悲の心深く、善事を思
|
|
|
カテゴリ:『本朝神仙記伝』の研究 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
#00433 2016.9.5
『本朝神仙記伝』の研究(51) -一路居士・道観・善輔-
●
|
一路居士(いちろこじ)はその姓氏を詳らかにせず。和泉国堺に住める隠士にして、僧・一休と同時の人なり。ある日一休、一路に問ひて、「万法皆道あり。如何にぞこれ一路とは云ふぞ」と云ひければ、一路これに答へて、「万事皆休すべし。如何にぞこれ一休とは云ふぞ」と云ひけるとぞ。
一路、嘗(かつ)て隠(いん)を或る山に卜(ぼく)し、世を終るまで詩歌に遊�
|
|
|
カテゴリ:『本朝神仙記伝』の研究 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |