| |
| #0082 2011.1.30 |
| 須佐之男命の罪の解除
|
 |
「ここに八百万神共に議(はか)りて、速須佐之男命に千位(ちくら)の置戸(おきど)を負はせ、また髭(ひげ)を切り、手足の爪をも抜かしめて、神(かむ)やらひやらひき。」『古事記』
「すなはち天児屋命(あめのこやねのみこと)に、その解除(はらえ)の太諄辞(ふとのりとごと)を掌(し)らしめて宣(の)らしむ。」『日本書紀』
「千位(ちくら)の置戸(おきど)」は、『日本書紀』では「千座(ちくら)の置戸(おきど)の祓具(はらえつもの)」となっており、つまりこれは、天照大御神が天石屋(あめのいわや)に隠れてこもることになった原因を作った須佐之男命を祓い清めるためのものであることがわかります。 #0076【須佐之男命の乱行】>>
『大祓詞(おおはらえのことば)』に「天津菅曾(あまつすがそ)を本刈断(もとかりたち)末刈(すえかり)切りて八針(やはり)に取辟(とりさき)て」とあるのはこのことを指しており、後に人間界に伝えられて、祓い清めの神具である「祓い串」となったものと思われます。
また『大祓詞』では、この須佐之男命の乱行を「天津罪(あまつつみ)」と呼び、罪の起源であるとされていますが、「祓」には穢(けが)れを祓う「禊祓(みそぎはらえ)」と、罪を祓う「解除(みそぎはらえ)」があり、この時は須佐之男命の罪を解除するためのものと考えられます。しかしあまりにもその罪が重く、祓具だけでは解除することができないため、髭や爪などの神体にまで及んだものとうかがわれます。(「禊祓」と「解除」の違いを簡単にいえば、穢れを祓うのは「身を濯(そそ)ぐ」で、罪を祓うのは「身を削(そ)ぐ」ということになります。自らの労力や財を削いで世のために施すことは、自らが犯した罪の解除になります。)
そしてこの罪の解除にあたり、天児屋命(あめのこやねのみこと)が中心となって解除の太諄辞(ふとのりとごと、太祝詞事)を奏上し、祓戸神(はらえどのかみ)に祈念したことが『日本書紀』に伝えられています。 #0060【禊ぎ祓えの神術】>> #0061【祓戸四柱神の誕生】>>
(フトノリトゴトについては前述したとおりです。 #0080【神楽の起源】>> )
「神やらひ」は「神遣ひ」ですので、追放したというよりは、ある神量(かむはかり)によって遣(つか)わせたという意味で、 #0070【須佐之男命による地軸の傾斜】>> つまりこの神事によって須佐之男命の天津罪のミソギハラエが完了し、新たな任務を遂行するため、再び地球に天降ることになったものと考えられます。
須佐之男命も、はじめから罪を犯そうという考えはなく、知らず知らずの内に罪を犯すことになったわけですが、それでも罪は罪として贖(あがな)わなければならないという厳しい掟律と、その罪が解除された後は、もはやそれにはこだわらないという明朗な世界が神仙界であり、また、「罪を憎んでその者を憎まず」というような清らかさもうかがわれます。
わたしたち人間も、悪意はなくても罪を犯していることは相当あるはずですが、祝詞の一節に「過(あやまち)犯すことの在らむをば、見直し聞き直し給ひて」とあるように、知らず知らずの内に犯している罪、咎(とが)、穢れを「祓へ給へ清め給へ」と祓戸神に祈念する神事が、今も日本の神道で行われています。 #0018【「はらひきよめ」という日本文化】>>
とくに六月晦日及び十二月晦日に宮中をはじめ日本全国の神社で斎行される「大祓祭」は、自分や家族のことだけではなく、また日本国のためだけでもなく、すべての地球人類の罪、咎、穢れを祓い清める神祭として今も続けられています。
犯した悪事を懺悔することも必要なことですが、知らず知らずの内に犯している罪はもっと深刻です。なぜなら当の本人が全く気づいていないわけですから、恐らく同じような罪を何度も繰り返すはずです。そうなると、また同じように禍事(まがこと)も繰り返し起こるわけで、永遠に悪循環から逃れることはできません。「自分は悪くない、悪いのは他人」という考え方は捨てて自分を見直し聞き直し、また神にも「過(あやまち)犯すことの在らむをば、見直し聞き直し給へ」と祈り、禍事(災難)が起こった時には「こうなったのは自分にも責任があるのでは?」と謙虚な心を忘れないことが幸福への近道だと思われます。 #0041【祈りのメカニズム(2)】>> #0047【祈りのメカニズム(6)】>> |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
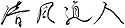
|
|
カテゴリ:日本の神伝 |
 |
| |
|
|
| |
| ▼関連記事一覧 |
 |
#0080 2011.1.21
神楽の起源
●
|
|
「天香山(あめのかぐやま)の五百津(いおつ)真賢木(まさかき)を根こじにこじて、上枝(ほつえ)に八坂勾璁(やさかのまがたま)の五百津の御(み)すまるの玉を取り著(つ)け、中枝(なかつえ)に八尺鏡(やたのかがみ)を取りかけ、下枝(しつえ)に白(しら)にぎて青にぎてを取り垂(し)で、この種々(くさぐさ)の物は、布刀玉命(ふとだまのみこと)布刀御幣(�
|
|
|
カテゴリ:日本の神伝 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
#0076 2011.1.2
須佐之男命の乱行
●
|
|
「ここに速須佐之男命、天照大御神に白(まお)したまはく、「我(あ)が心、清明(あかき)故に我(あ)が生みし子(みこ)手弱女(たわやめ)を得つ。これによりて言(まお)さば、自ずから我(あれ)勝ちぬ」と云ひて、勝(かち)さびに天照大御神の営田(みつくた)の畔(あ)を離ち、その溝(みぞ)を埋め、またその大嘗(おおにえ)聞こしめす殿に屎(くそ)まり散ら�
|
|
|
カテゴリ:日本の神伝 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
#0061 2010.10.20
祓戸四柱神の誕生
●
|
「次にその禍(まが)を直さむとして成りませる神の名(みな)は、神直毘神(かむなおびのかみ)、次に大直毘神(おおなおびのかみ)、次に伊豆能売神(いずのめのかみ)」『古事記』
神直毘神と大直毘神の関係も禍津日神(まがつひのかみ)と同様ですが、 #0060【禊ぎ祓えの神術】>> この神は禍事(まがごと)を直そうという伊邪那岐神の感動�
|
|
|
カテゴリ:日本の神伝 |
続きを読む>>
|
|
|
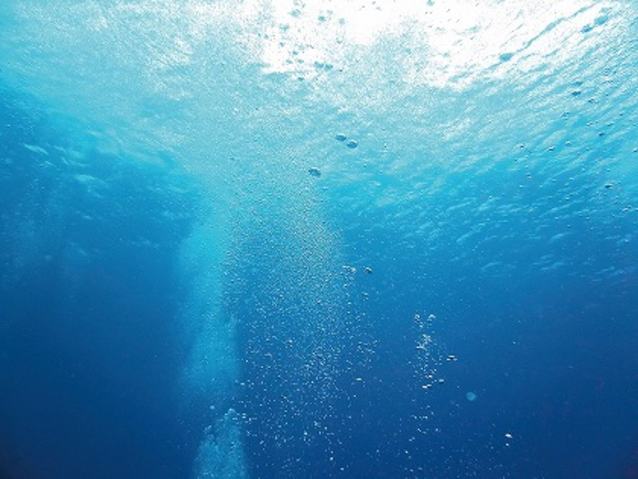
|
|
 |
#0060 2010.10.14
禊ぎ祓えの神術
●
|
|
「高天原(たかまのはら)に神留(かむづまり)ます神漏岐(かむろぎ)神漏美(かむろみ)の命(みこと)以(もち)て。皇御祖神(すめみおやかむ)伊邪那岐命(いざなぎのみこと)。筑紫(つくし)の日向(ひむか)の橘(たちばな)の小門(おど)の阿波岐原(あわぎはら)に。身滌(みそぎ)祓ひ給ふ時に生(あれ)ませる祓戸之大神等(はらえどのおおかみたち)。諸(も�
|
|
|
カテゴリ:日本の神伝 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
#0047 2010.8.9
祈りのメカニズム(6)
●
|
古代中国の晋(紀元前1100年頃~紀元前378年)の時代、六卿の一人であった中行文子の国がまさに滅びようとしていました。そこで祭祀長を呼びつけ、「君が毎日我国の繁栄を祈祷(きとう)しているのに、なぜこんなことになってしまったのか。神への供え物が足りないのか、それとも君の祈祷が悪いのか」と大いに責めました。そこで祭祀長が答えました。
「先君�
|
|
|
カテゴリ:玄学の基本 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |