| |
| #0018 2010.3.3 |
| 「はらひきよめ」という日本文化
|
 |
肉体から発する情の力は非常に強く、魂が魄を制するのはとても難しいことですが、古代日本人は自然にその智恵を身につけていました。 #0015【人間の本性は善か悪か?(1)】>> #0016【人間の本性は善か悪か?(2)】>> #0017【心の中の葛藤とは?】>> それは、諸外国から儒教や仏教、その他の教学や文化が流入する以前から日本に存在していた神道(かむながらのみち)の中にみることができます。
神道では清浄を第一義としますが、「はらいきよめ」という概念は世界的にみても珍しいものです。まず「はらい」とは「張る霊(はるひ)」のことで、精神がほどよく緊張した状態を表しています。また「きよめ」とは「気蘇め(きよめ)」であり、気が蘇るという意味です(ちなみに「蘇る」は「黄泉帰る」)。つまり「はらいきよめ」とは、「気を蘇らせてほどよく緊張した精神状態を保つ」ということになります。
また「穢れ(けがれ)」とは「気枯れ」であり、「罪」とは「包み」が約(つづ)まったもので、魂を包み隠すという意味です。つまり「罪、穢れを祓い清める」とは、「魂が魄によって包み隠され、気が枯れてしまった状態から、再び精神が緊張を取り戻して気が蘇える」という意味になり、魂が魄を制する状態にリセットして、精神を健全(かむながら)に保つ手段であることがわかります。
具体的には、まず神社でのお祓いが思い浮かぶでしょう。その所作は、まず神主がやまとことばによる「禊祓詞(みそぎはらえのことば)」を奏上して言霊(ことだま)の力によって祓い清め、さらに木の棒に麻と紙垂(しで)が結びつけられた大幣(おおぬさ)を頭の上で左右に揺り動かし、その清風によって邪気を祓います。(麻などの植物や、それを原料として作られた和紙には邪気を祓う力があるとされています。)
日本の神社では、今でも毎日神主がやまとことばによる祝詞(のりと)を奏上し、また定められた日ごとに神祭が執り行われていますが、一般の日常生活をみても、正月の初詣にはじまって、節分の豆まき、雛祭り、端午の節句の行事、七夕祭り、神社の夏祭りや秋祭りなど、季節ごとに祓い清めの行事が民間の風習として残っています。
食前やトイレの後に手を洗い、家に帰るとうがいをする行為も邪気祓いの概念からくるものですが、こういった例は枚挙にいとまがなく、日本の文化は「はらいきよめ」と密接に結びついていることがわかります。
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
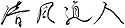
|
|
カテゴリ:玄学の基本 |
 |
| |
|
|
| |
| ▼関連記事一覧 |
 |
|
|
 |
#0016 2010.2.22
人間の本性は善か悪か?(2)
●
|
また、魂のはたらきを性(やまとことばではココロネ)といい、魄のはたらきを情ともいいますが、これだけ聞くと、情というものは悪しきものであると思われるかもしれませんが、決してそういうわけではありません。
性にしたがう情であれば、つまり魄が魂にしたがっているわけですから、これは人間にとって最も善い状態といえるでしょう。しかし性にしたがわない情は、
|
|
|
カテゴリ:玄学の基本 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
#0015 2010.2.17
人間の本性は善か悪か?(1)
●
|
人間の本性が善であるか悪であるかについては、主に儒教などで語られてきましたが、日本古学では次のように説かれています。
実は人間の霊魂の活用には、魂(こん)と魄(はく)の二種類の区別があります。魂魄(こんぱく)というのは漢字の音読みですが、これをやまとことばでは、魂を「みたま」あるいは「をだましひ」、魄を「みかげ」あるいは「めだましひ」と�
|
|
|
カテゴリ:玄学の基本 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |