| |
| #00198 2012.10.25 |
| 清明伝(1) -災いは穢れから-
|
 |
「畏(かしこ)くも神代(かみよ)の昔、伊邪那岐命の黄泉(よみ)の穢れに交じり給ひしより初めて妖神邪気世に出現し、天下の人民をして正道を誤らしめ、悪人に福し善人に禍して世界を擾乱(じょうらん)せむとし、また人の私欲を進めて正心を昏(くら)まし、その人の私心に乗りて悪欲を長ぜしめるに至る。」
これは明治の謫仙(たくせん)宮地水位先生の手記の一節ですが、祝詞に「禍神(まがかみ)の禍事(まがごと)に相交(あいまじ)こり相口会(あいくちあ)う事無く」とあるのは、このような妖神邪気の憑纏(ひょうてん)を受けないようにという意味です。 #0044【祈りのメカニズム(4)】>> #0045【祈りのメカニズム(5)】>>
神伝によれば、禍事・非事(ひがごと)という災いのそもそもの根元は、実に黄泉(よみ)の穢れに触れることより惹起(じゃっき)しますので、神道においては諸々の罪穢れを祓い清める神事修法が伝承され、修道祭祀の根本となっていることからも、日本が神の道の宗国である明証といえるでしょう。 #0082【須佐之男命の罪の解除】>>
「穢れ」は「気枯れ」でもあり、生気(清気)が枯れることによって意気消沈すると、運気も下降して災いを招き、またその生気が全く枯渇してしまうと遂には死に至ることとなります。 #0018【「はらひきよめ」という日本文化】>>
その穢れを払拭する清祓(せいばつ)のことについては、わたしたちの日常生活の上でも大変重要と思われますので、本居宣長先生の『玉鉾百首』に詠まれた歌を参考にして考究してみたいと思います。
「家も身も国も穢すな穢らはし、神の忌みますゆゆしき罪を」
その意味は「家内も身体も国内も穢すことなく清浄にせよ、なぜなら穢れは神が忌み給う忌々(ゆゆ)しき罪であるからである」というもので、穢れは神が忌み給う罪であることを表しています。
「穢れをし罪とも知らに禊がずて、默止(もた)ある人を見るがいぶせき」
「知らに」とは「知らずに」という意味で、「默止ある」とは、「なすべきことをせずにそのままにしておく」ことをいいます。また「いぶせき」は、「幽鬱で心がもやもやしてさっぱりしない」ことで、穢れを罪とは知らずに禊ぎを行わない人を見ると、きたなくむさく思われることを表しています。
「罪しあらば清き川瀬に禊ぎして、速秋津姫(はやあきつひめ)にはや明らめよ」
速秋津姫神(はやあきつひめのかみ)は祓戸神(はらえどのかみ)の一神ですが、とくにこの神を詠まれているのは、「清め」ということに最も功のある神だからです。この一首の意味は、「もし穢れがあるならば、清らかな川瀬に入って身を滌(あら)い、速秋津姫神に祈請して速やかに祓い清めよ」ということです。 #0061【祓戸四柱神の誕生】>>
キリスト教にも「原罪」という概念が存在しますが、これは『創世記』中の伝承に基づいたもので、エデンの園において人類の始祖であるアダムとイヴが、蛇の誘惑によって「善悪の知識の木の実」(いわゆる「禁断の果実」)を食べてしまい、怒った主なる神によって楽園を追放されたというものです。そしてこれが、人類が最初に犯したとされる罪で、その罪が人間の本性を損ね、あるいは変えてしまったため、以来人間は神の救済なくして克服し得ない存在となったという教えです。
カトリックでは、洗礼を受け、キリストの奇跡を信じることによってこの原罪が取り除かれるとされていますが、日本の神伝が甚(はなは)だしく簡略化されて訛伝(かでん)したものであることがわかります。 #0093【世界太古伝実話(2) -古伝と神話-】>>
「枉事(まがこと)を身滌(みそが)せれこそ世を照らす、月日の神は成り出でませれ」
「身滌せれこそ」は「身滌(みそぎ)を行えばこそ」、「成り出でませれ」は「生れ出でました」という意味です。神典によると、伊邪那岐神が禊ぎ祓えの神術を行い、黄泉(よみ)の穢れを祓い清められた後、天地に輝いて世を照らす日月の貴神(天照大御神・須佐之男命)が化生されました。ならば世の人も、身に穢れがある時は身滌ぎを行って速やかに祓い清めるべきでしょうという意味です。 #0060【禊ぎ祓えの神術】>> #0062【三貴子の誕生】>>
本居先生が百首の内、この歌を巻尾に詠まれているのも、偶然ではないと思われます。察するに、万霊万物を生み成した伊邪那岐神は天之御中主神の後天的存在ともいえますが、この大神が伊邪那美神を失うという大凶事によって黄泉の穢れに触れ給い、その後の禊ぎ祓えによって完全に邪気を払拭した直後に日月の貴神が化生し、伊邪那岐神が「大(いた)く歓喜(よろこ)びて」というほどの大吉事が起こったということは、これこそが天地万物造化(天地陰陽の運行)の玄理原則、つまり自然の摂理であるということになります。 #0030【天地万物造化のはじまり】>>
激しい雷雨の後に虹がかかり、大嵐が去った後は清々しい朝を迎えることもこれと同じで、神典や自然界には学ぶべきことが多くあります。 #0056【神々の怒り】>> #0057【女神の御心 -母性愛の起源―】>> #0058【日本人として】>> |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
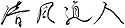
|
|
カテゴリ:清明伝 |
 |
| |
|
|
| |
| ▼関連記事一覧 |
 |
#0060 2010.10.14
禊ぎ祓えの神術
●
|
|
「高天原(たかまのはら)に神留(かむづまり)ます神漏岐(かむろぎ)神漏美(かむろみ)の命(みこと)以(もち)て。皇御祖神(すめみおやかむ)伊邪那岐命(いざなぎのみこと)。筑紫(つくし)の日向(ひむか)の橘(たちばな)の小門(おど)の阿波岐原(あわぎはら)に。身滌(みそぎ)祓ひ給ふ時に生(あれ)ませる祓戸之大神等(はらえどのおおかみたち)。諸(も�
|
|
|
カテゴリ:日本の神伝 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
#0058 2010.10.3
日本人として
|
|
以上のように神代第二期中は、伊邪那岐・伊邪那美神の御心が一たび感動されるごとに、直ちに化生神が出顕するほどの気運ですが、その感動とは本魂が動かれるのではなく、ただ情が動くものと考えられます。伊邪那岐神の女神を偲ぶ愛情が変じて遂に怒りとなりましたが、建(たけ)き神々が化生した後はさらに怒ることはなく、また、伊邪那美神の恨みの情が変じて怒りとなり�
|
|
|
カテゴリ:日本の神伝 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
#0057 2010.9.28
女神の御心 -母性愛の起源-
●
|
|
「最後(いやはて)にその妹(いも)伊邪那美命、身(み)自ら追ひ来ましき。ここに千引石(ちびきいわ)をその黄泉比良坂(よもつひらさか)に引き塞(さ)へて、その石(いわ)を中に置きて、各(あい)対(む)き立ちて事戸(ことど)を度(わた)す時に、伊邪那美命言(まお)さく、「愛しき我(あ)が那背命(なせのみこと)かくしたまはゞ、汝(いまし)の国の人草(�
|
|
|
カテゴリ:日本の神伝 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
#0056 2010.9.23
神々の怒り
●
|
|
「ここにその妹(いも)伊邪那美命(いざなみのみこと)を相(あい)見むと欲(おもお)して黄泉国(よみのくに)に追ひ往(ゆ)きましき。ここに殿の滕戸(さしと)より出で向へし時、伊邪那岐命(いざなぎのみこと)語りて詔(の)りたまはく、「愛しき我が汝妹(なにも)の命(みこと)、吾(あ)と汝(いまし)と作りし国、未だ作り竟(お)へず。かれ、還(かえ)るべ�
|
|
|
カテゴリ:日本の神伝 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
#0030 2010.5.10
天地万物造化のはじまり
|
「天地(あめつち)初めて発(ひら)けし時、高天原(たかまのはら)に成りませる神の名(みな)は、天之御中主神(あめのみなかぬしのかみ)、次に高御産巣日神(たかみむすびのかみ)、次に神産巣日神(かみむすびのかみ)。この三柱(みはしら)の神は、みな独神(ひとりがみ)成りまして、隠身(かくりみ)なり。」『古事記』
さて、天之御中主神 |
|
カテゴリ:日本の神伝 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
|
|
 |