| |
| #00192 2012.9.19 |
| 『古事記序文』解説(4)
|
 |
「ここに天皇(すめらみこと)詔(の)りたまはく、「朕(われ)聞く、諸家の賷(も)てる帝記及び本辞、既に正実に違(たが)ひ、多く虚偽を加ふと。今の時に當(あ)たりてその失(あやまり)を改めずは、未だ幾年(いくとせ)を経ずしてその旨(むね)滅びなむとす。これ乃(すなわ)ち邦家の経緯、王化の鴻基(こうき)なり。かれ、これ帝記を撰録し、旧辞を討覈(とうかく)し、偽りを削り実(まこと)を定め、後葉(のちのよ)に流(つた)へむと欲す」とのたまふ。」
(現代語訳:清風道人)
「ここに天武天皇は詔(みことのり)を下し給い、「私の聞くところによれば、諸家に伝えられている帝紀及び本辞には、既に真実と違い、虚偽が加わったものが多いとのことである。今の内にその誤りを改めておかなければ、何年か経る間にその正旨は滅んでしまうであろう。そもそも帝紀及び本辞は我が国の成り立ちと国体の礎(いしずえ)を伝えたものである。それ故、偽りを削って真実を定め、後の世に伝えたいと思う」と仰せられました。」
このことからわかるように、『古事記』は新たに考えて作られた物語ではなく、当時の諸々の家系に伝えられていた帝紀(歴代の皇統を記した書)や旧辞(太古の神代の伝承を記した書)から虚偽の説を削り、後世に真実を伝えるために選集された書であるといえます。
これに対して『日本書紀』は、神武天皇以降の部とそれ以前の神代の部では大きく趣が異なり、神代の伝承は「一書(あるふみ)に曰く、・・・」また「一書に曰く、・・・」とあるように、真偽に関わらず、諸家に伝承されて来た大同小異の様々な伝が記されており、『古事記』を補う書として見るべきでしょう。
これらのことから、『古事記』『日本書紀』は一個人の思想から出た人造作為のものではなく、太古の昔から伝えられた天然自然の古伝であることは明白です。 #0093【世界太古伝実話(2)-古伝と神話-】>>
「時に舎人(とねり)有り。姓は稗田、名は阿礼、年はこれ二十八。人となり聡明にして目に度(わた)れば口に誦(よ)み、耳に拂(ふ)るれば心に勒(しる)す。即ち阿礼に勅語して、帝皇(すめらみこと)の日継(ひつぎ)及び先代の旧辞を誦(よ)み習はしむ。然(しか)れども運(とき)移り世異(かわ)りて、未だその事を行はざりき。」
(現代語訳:清風道人)
「ちょうどその頃、姓は稗田、名は阿礼、年は二十八歳になる者が官人として仕えていました。この者は生まれつき聡明で、目にしたものは全て口に出して読むことができ、耳にしたことは心に記すことができました。そこで天皇は阿礼に勅語して、天皇の日嗣(ひつぎ)及び先代の旧辞を読み習わせました。しかしながら天武天皇が崩御され、その事を完成するには至りませんでした。」
現在の日本語学界をはじめとするアカデミズムの世界では、漢字渡来以前の日本に固有の文字は存在しなかったとする説が広く支持されており、『古事記』についても、稗田阿礼が記憶していたことを暗誦し、それを太安万侶(おおのやすまろ)が漢字で書き留めたとされていますが、「目に度(わた)れば口に誦(よ)み」とあり、また「帝皇(すめらみこと)の日継(ひつぎ)及び先代の旧辞を誦(よ)み習はしむ」とあるように、稗田阿礼は暗誦したのではなく、種々の文字で書かれた書を声に出して読み上げたとする方が自然でしょう。
稗田阿礼がいかに聡明であったとしても、これだけの膨大なストーリーや、数多くの御神名、また歴代天皇の御名やエピソードを全て記憶していたと考える方がむしろ不自然で、恐らく阿礼は各地で使われていた様々な神代文字を読むことができ、阿礼が読み上げる伝承を元にして、漢語に勝れた太安万侶が漢字を使用して編集したというのが真相と考えられます。
(「漢字渡来以前の日本に固有の文字は存在しなかった」と考える人は、「太古の日本は野蛮だった」という考えが先入主となっているものと思われます。 #0097【世界太古伝実話(6)-先入観による弊害-】>> また、『仙境異聞』中で、山人界での文字の教わり方について「一字ごとに数百字を習う」と仙童寅吉が語っているのも興味深いことです。 #0149【『仙境異聞』の研究(14) -山人界の勉学-】>> )
ちなみに、「稗田氏」は、平安時代初期の弘仁6年(815年)に嵯峨天皇によって編纂された古代氏族の名鑑である『新撰姓氏録』には見えませんが、『弘仁私記』には「天細女命(あめのうずめのみこと)の後なり」とあり、また『西宮記』にも稗田氏について「猿女(さるめ)」と縁が深いことが記されており、阿礼は天宇受売命(あめのうずめのみこと)の後裔で、その縁によって天皇命(すめらみこと)に仕えていた女官であったものとうかがわれます。 #0174【皇孫命、天降る】>> #0178【猿田彦神と天宇受売命の功業】>> |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
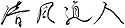
|
|
カテゴリ:日本の神伝 |
 |
| |
|
|
| |
| ▼関連記事一覧 |
 |
#00178 2012.6.28
猿田彦神と天宇受売命の功業
|
|
「かれ、ここに天宇受売命(あめのうずめのみこと)に詔(の)りたまはく、「この御前(みさき)に立ちて仕へ奉りし猿田毘古大神(さるたびこのおおかみ)をば、専(もは)ら顕(あらわ)し申せる汝(いまし)送り奉れ。またその神の御名は汝(いまし)負(お)ひて仕へ奉れ」とのりたまひき。ここを以て猿女君(さるめのきみ)等(ら)、その猿田毘古の男神の名を負ひて、�
|
|
|
カテゴリ:日本の神伝 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
#00174 2012.6.4
皇孫命、天降る
●
|
|
「ここに日子番能邇邇芸命(ひこほのににぎのみこと)、天降りまさむとする時に、天(あめ)の八衢(やちまた)に居(い)て、上(かみ)は高天原を光(てら)し、下(しも)は葦原中国(あしはらのなかつくに)を光(てら)す神ここにあり。かれ、天照大御神・高木神(たかぎのかみ)の命(みこと)以(もち)て天宇受売神(あめのうずめのかみ)に詔(の)りたまはく、「�
|
|
|
カテゴリ:日本の神伝 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |