| |
| #00396 2016.1.25 |
| 『本朝神仙記伝』の研究(14) -漆部造麿が妻-
|
 |
漆部造麿(ぬりべのみやつこまろ)が妻は何氏なるを知らず。大和国宇多郡漆部里の人なり。
その性、廉潔にして清浄を好み、少しも穢れ無き好女なり。常に魚肉だに食せず、専ら菜蔬(さいそ)のみを食とせり。七人の子有れども、家貧にして衣服無きを以て、藤蔓(ふじづる)を用ひ、物を綴(つづ)りて身に纏(まと)ひたりと云ふ。
然(しか)れども日々沐浴を怠らず身を清潔にして、野に出て菜の類ひを取り来(きた)りて羹(あつもの)とし、これにて飢を凌ぎ、家内を掃ひ清めて、母子共に正しく座して食事を為す、その気調(みさお)の美(うるわ)しきこと、宛(さなが)ら天上の客の如くなりしと云ふ。
かくて神仙その節操にや感応坐しけむ、ある年の春、野辺に出て菜を取りて常の如く羹とし、母子共にこれを食したりしが、不測にもその菜の中に仙草の交りて有りけるにや、これを食ひしより、心澄み渡り身健やかになりて、また老ると云ふことなく、その後数多(あまた)の年月を経、母子共に仙人と成りて、遂に天上に飛翔し去りけるとかや。
母子がその仙薬の羹を食したるは、何れの時代なりしや定かならねど、飛翔して仙去したるは、正しく孝徳天皇の白雉五年のことにて有りけるとぞ。 #0168【神仙の存在について(6) -仙去の玄法-】>>
厳夫云、本伝は『日本霊異記』に載せたるを採りてこゝに挙げたり。この漆部造麿が妻の野辺に出て採り来れる菜に仙薬の交りて有りけるにやとある、仙薬とは如何なるものにて有りしか、今これを知る由(よし)無けれど、これに思ひ合すべきは、『抱朴子』仙薬巻に五芝(石芝、木芝、草芝、肉芝、菌芝)の中の草芝(そうし)のことを挙げて、獨搖芝(どくようし)、牛角芝、龍仙芝、麻母芝(まぼし)、珠芝(しゅし)、白符芝(はくふし)、朱草芝、五徳芝、龍銜芝(りゅうかんし)等の九種の名を載せ、各々その形状をも説きたり。
今その二、三を云はむに、「牛角芝は虎寿山(こじゅさん)及び呉坂(ごはん)の上等に生ず。状(かたち)葱に似て特生す。牛角の如し。長さ三十四尺にして青色なり。粉末にして方寸匕(ほうすんさじ)を服すること日に三度し、百日に至れば即ち千歳を得る」と云ひ、また「麻母芝は麻に似て茎は赤色、花は紫色」と云ひ、また「龍仙芝は状(かたち)昇龍の相負ふに似たり。葉を以て鱗(うろこ)と為す。その根は即ち蟠龍(はんりゅう、とぐろを巻いた龍)の如し。一枚を服すれば千歳を得る」と云ひ、また「龍銜芝は常に仲春を以て三節十二枚を生ず、その根、座せる人の如し」等、各々細かにこれを説き、その末に「この草芝もまた凡そ百二十種あり。皆陰乾(かげぼし)にす。これを服すれば、即ち人をして天地と相畢(あいおわら)しむ。或は千歳二千歳を得る」とあり。
これに依れば、草芝は凡そ百二十種もあるものなれば、その中には普通の野菜に似たるものも多かるべし。既に余(よ)も、ある真形図の末に四種の仙薬の図を載せたるを見しこと有りしが、その中の養神草の如きは、全く普通の野菜に異なること無き形のものなりき。これも必ずその百二十種中の一種なること云ふを待たず。さては漆部造麿が妻の羹として服したるも、蓋(けだ)しこの類ひのものにてありしならむ。 #0325【『異境備忘録』の研究(10) -諸真形図-】>> #0343【『異境備忘録』の研究(28) -神仙界の養生法-】>>
今案ずるに、神仙得道の法、必ずしも一つに非ず。還丹修練の効によりてこれを得る者あり。霊芝仙薬を服するによりてこれを得る者あり。積善陰徳の功によりてこれを得る者あり。図をおび符を服するによりてこれを得る者あり。精思純想によりてこれを得る者あり。霊章秘文を唱するによりてこれを得る者あり。この他なお種々ありといえども、それはただ分け入る門を異にするに過ぎざるのみにて、要するに至誠が極まり神明の感応を得る結果に外ならず。
而(しか)してその何れの門より入りたるに拘はらず、道を得る者は、修練の力とか霊薬の力とか、その他修むる所の何かの力によりて、この凡胎の凡骨肉を変化し、所謂(いわゆる)換骨脱体して神仙の霊胎と成るに非ざれば、道は得られざるものと知るべし。 #0226【尸解の玄理(5) -本身の練蛻-】>> #0230【尸解の玄理(9) -求道の真義-】>>
然ればこの漆部造麿が妻並に七子等は、皆その仙薬の力に因りて道を得たるものなること、また云ふを待たざるべし。
(清風道人云、真人の現界生活における薄幸は古今東西に見られますが、この漆部造麿の妻の伝は、常に心身の清浄を保つべく清祓に努め、心魂の清明純陽なる徳を失わず、不幸な境涯を嘆くことなく節操を守り通せば、やがて幽助によって何らかの秘訣を授かり、終には神仙の道を得るに至ることを示した逸話といえるでしょう。 #0159【『仙境異聞』の研究(24) -人の真道とは?-】>> #0329【『異境備忘録』の研究(14) -肉転仙の幽助-】>> #0377【『異境備忘録』の研究(62) -真人の薄幸-】>> ) |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
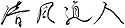
|
|
カテゴリ:『本朝神仙記伝』の研究 |
 |
| |
|
|
| |
| ▼関連記事一覧 |
 |
|
|
 |
#00343 2015.3.10
『異境備忘録』の研究(28) -神仙界の養生法-
●
|
|
「明治八年二月二十日、玄丹先生に伴はれて日向の高千穂峰に登る。この時、三十四符を受く(天満宮の楼門より行く)。この山、八合より上、大熱大風し上るべからず。雄黄(いおう)臭ふ。匍蔔(はらばい)して上る。谿水(けいすい)雷の如し。御天上に登る。こゝに鉾あり。所謂(いわゆる)逆鉾(さかほこ)なり。この傍、赤色神忽(たちま)ち顕れ忽ち隠る。この辺りにて�
|
|
|
カテゴリ:『異境備忘録』の研究 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
#00329 2014.12.15
『異境備忘録』の研究(14) -肉転仙の幽助-
|
|
「明治九年三月五日、川丹(せんたん)先生、清定君(せいじょうくん)の御使に来る。この時、余(よ)問ふに、「友人に仙道を請慕する者あり、神界へ伴ひ給ふ事は如何(いか)に候や」、答に、「神の許容又御召しの外(ほか)、この川丹等濫りに伴ひ参る事叶はず。今日神界を窺ふとも、明日又その界を見んと思へども許容なき時は見る事能(あた)はず。清浄利仙君、杉山清�
|
|
|
カテゴリ:『異境備忘録』の研究 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
#00325 2014.11.21
『異境備忘録』の研究(10) -諸真形図-
●
|
「明治十年一月二十九日黎明、小童君に伴はれて神集岳大永宮に至る。午十二時頃、要用万事済みて帰る時、川丹先生の室に入らせ給ふ。この時、諸々の真形図(しんぎょうず)を拝見す。その図各々左の如し。
風元山真形図。游岳真形図。天関界図。冠長山真形図。河岳八元図。元都玉京山紫蘭真形図。浮根人長山真形図。玉宝五元真形図。混沌七化真形図。集霊山真形図。八会
|
|
|
カテゴリ:『異境備忘録』の研究 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
|
|
 |
#00226 2013.4.8
尸解の玄理(5) -本真の練蛻-
●
|
|
尸解(しか)の道は、道書に「尸解は形の化なり、本真の練蛻(れんぜい)なり、これ仙品の下弟といえどもその稟受(ひんじゅ)して承(う)くるところは未だ必ずしも軽からざるなり」とあり、仙縁ある人である程度の道養の徳を積むに至れば必ず行われるべきもので、屍(しかばね)を解くという解化の過程が極めて短時間に行われ、大いに常態と異なるところから一種異様な�
|
|
|
カテゴリ:尸解の玄理 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |