| |
| #00239 2013.6.25 |
| 『幽界物語』の研究(9) -仙境の気候-
|
 |
『幽界物語』( #0231【『幽界物語』の研究(1) -概略-】>> )より(現代語訳:清風道人)
参澤先生 「仙境にも昼夜や明闇はあるのか。また十二時の定めはあるか。また、かの界にいる時は一日あるいは一刻なども現界のように長短に思うのか。」
幸安 「昼夜共に明るいことは、この界の白昼のようです。日輪の出入りは見えますが、光を借りることはありません。そのため寝ることも無く、眠たいこともありません。時刻はこの人界の一時も、仙境にいる内は久しいように思われます。
さて、十二時の分かちは気支(きし)と申す虫が啼くのを聞いて知ります。この虫は、大きさは蝉ほどで金色の美しい虫です。羽を振るわせて鳴きます。その声は時刻の名を呼ぶように聞こえます。」
『日本書紀』や『丹後国風土記』に見える、浦島子(うらのしまこ、浦島太郎)が海中の幽境に入って三年後、帰郷してみると既に三百年も経過していたという伝承や、中国の『述異記』の、晋の時代、王質という木こりが薪を採りに信安郡の石室山入り、そこで数人の童子が歌いながら碁を打っているのを見物し、対局を見終って斧を取り上げるとその柄(え)が腐っており、下山してみると既に五百年の歳月を経ていたというような仙伝から考えてみると、三次元世界である現界で考えられている時間と空間に関する認識と、四次元以上の高次元世界である幽界を含む宇宙の実相からみた時間と空間の正体に、どれほどの隔たりがあるかということがおぼろげながら分かってきます。 #0155【『仙境異聞』の研究(20) -幽界の謎-】>>
参澤先生 「風雨雷鳴などすることもあるのか。蓑笠(みのがさ)は用いるのか。」
幸安 「雷鳴はありません。雨が降ることはありますが、身には触れず、少しも濡れません。そのため蓑笠はありません。ただし、青い木葉を蓑のように編んだ衣は見ます。」
参澤先生 「仙境でも月や雪、花を見て楽しむことはあるのか。月も光があるのか。雪も降るか。花も咲き変わるのか。」
幸安 「月は白く見えます。雪が降り積もることもあります。ただし、身には触れず、冷たくはありません。花は、桜、梅、牡丹(ぼたん)、芍薬(しゃくやく)など、諸々四季によって花が咲きます。月、雪、花を愛(め)で、山水を賞し、それに寄せて歌を詠み、詩を吟じ、仙境の楽、世のありさまなどを言挙(ことあ)げします。」
参澤先生 「幽境は日光がなくても明るいようだが、物の陰陽はあるのか。また山中ならば、物音が木霊(こだま)のように響くことはないのか。また山中に花や落葉が舞うことはないのか。あるいは家の中に塵(ちり)が溜まることはあるのか。衣服が破れ、身に垢が付くこともあるのか。」
幸安 「日に向かって立った時も身の影は無く、四方が明るいのです。物を鳴らす音も向こうへ響くことはありません。山中に落花や落葉もありますが、その色はとても綺麗です。何事をしても塵や埃(ほこり)が溜まることは全くありません。衣服はいつまでも新しく、破れたりしわになることはありません。身に垢が付いて臭気が出るなどということは一切ありません。」
参澤先生 「お前が幽界に入る時の身の心持や、四季の時候の様子はどうか。」
幸安 「幽境に移ってからは現界とは違い、身のことは、例えば夏に木陰で涼しい風が体に触れた時のように、少し酒に酔って快いという感じに似ています。また、気候は四季共に3月頃の長閑(のどか)な日中で野山に遊ぶように心清らかで陽気です。」
「幽界」といえば、何となく暗い様子をイメージされる方もおられると思いますが、それは現界において、夜間に照明を照らした部屋から外は見ることができず、逆に外からは室内を見通せることなどから連想されるもので、むしろこの仙境などは明るすぎるために現界からは見えないといった方が適切でしょう。 #0023【この世界だけがすべてではない】>>
いわゆる「理想郷」については、旧約聖書の『創世記』に登場する「エデンの園」、ケルト神話の「アヴァロン」、ギリシャ神話の「エリュシオン」、チベットの「シャンバラ(シャングリ・ラ)」、陶淵明によって著わされた「桃源郷」など、世界中に伝承が見られますが、そこに共通しているのは「物理的にも社会的にも衛生的な場所で、生活は質素で、厳格に律せられた社会」というもので、恐らくは世界中に存在するこの種の幽境の消息が漏れ伝わったものと思われます。 #0237【『幽界物語』の研究(7) -仙境の礼節-】>>
参澤先生より書簡で問 「仙界では日中でも影は無く、物音も響くことが無いと清玉(幸安の幽名)より承っていますが、いかがでしょうか。」
利仙君より答 「神境で影が無いのは身より光明を発する故、日の裏でも影は無い。物音に響きが無い理(ことわり)は幽界の秘事故に申し難い。」
参澤先生より書簡で問 「幽界の人々の身の光明はどこから出るのでしょうか。仏像のように頭から発するのでしょうか。」
利仙君より答 「神たち、仙人、山人、異人など、光明は総身五体より出でる。愚賓は口より光明を出す。妖魔は目より光を出す。仏者が頭より光を発するなどは術によって致すことである。」
神伝には、天照大御神が天石屋(あめのいわや)に身を隠したことによって高天原が暗黒となったこと、大国主神の和魂神である大物主神が海原を照らしながら依り来たこと、事代主神が飛び去った時は御身の光が二丘二谷の間に渡り、あるいは猿田彦神は「上(かみ)は高天原を光(てら)し、下(しも)は葦原中国(あしはらのなかつくに)を光(てら)す神」であることなどが伝えられていますが、仙境の人が身体から光明を発することについては、仙童寅吉も同様のことを述べています。 #0157【『仙境異聞』の研究(22) -穢火は魂をも穢す-】>>
またこのことについては、釈迦が悟りを得た時に身体が光明に包まれ(その実は霊胎凝結 #0161【『仙境異聞』の研究(26) -原始仏教の本質-】>> )、あるいは宮地水位先生が尸解(しか)された際、棺中より大光芒が発せられたということなどを考え合わせれば、誠に興味深いものがあります。 #0224【尸解の玄理(3) -実在する尸解仙-】>>
(古神道(神仙道)の使魂(脱魂)法を修している内に、両目の脇や瞼の下あたりにピンポン球状の光体が出現し、また数個の光の小玉が眼前で旋転する場合があり、しばらくの間は日常生活中においてもこの現象が続くことがありますが、これらは修業の初階梯によく起こる現象で、火色なら魂気で濃い水色なら魄気、また白色なら分魂の出顕です。 #0015【人間の本性は善か悪か?(1)】>> #0222【尸解の玄理(1) -神化の道-】>> #0232【『幽界物語』の研究(2) -幸安の幽顕往来-】>> ) |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
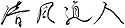
|
|
カテゴリ:『幽界物語』の研究 |
 |
| |
|
|
| |
| ▼関連記事一覧 |
 |
|
|
 |
|
|
 |
#00224 2013.3.27
尸解の玄理(3) -実在する尸解仙-
●
|
|
尸解(しか)が果たして本当に人間に可能か?という問題については、古来の仙伝にも枚挙にいとまない伝承があり、その内、著名な日本人に関しては宮地厳夫先生の『本朝神仙記伝』にもまとめられていますが、またそれ以外にも明治の謫仙(たくせん)宮地水位先生をはじめ、大正、昭和、平成の現代においてもめでたく仙去されたと考えられる真人が存在しています。 |
|
カテゴリ:尸解の玄理 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
#0023 2010.3.31
この世界だけがすべてではない
|
|
わたしたちが日常生活をおくっているこの世界を、やまとことばで「あらわよ(顕界)」といい、わたしたちの五感で感知できない異次元世界を「かくりよ(幽界)」といいます。そして宮地水位先生の『異境備忘録』に「幽界は八通りに別れたれども、またその八通りより数百の界に別れたり」とあるように、この幽界には、尊い神々の世界をはじめ、神の眷属(けんぞく)の世界�
|
|
|
カテゴリ:玄学の基本 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
#0015 2010.2.17
人間の本性は善か悪か?(1)
●
|
人間の本性が善であるか悪であるかについては、主に儒教などで語られてきましたが、日本古学では次のように説かれています。
実は人間の霊魂の活用には、魂(こん)と魄(はく)の二種類の区別があります。魂魄(こんぱく)というのは漢字の音読みですが、これをやまとことばでは、魂を「みたま」あるいは「をだましひ」、魄を「みかげ」あるいは「めだましひ」と�
|
|
|
カテゴリ:玄学の基本 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |