| |
| #00465 2017.3.17 |
| 無病長生法(9) -摂生総論-
|
 |
道人(川合清丸大人)、先に無病長生法本論を著はすの後、苟(いやしく)も摂生の事に係れる書籍は得るに任せて閲読せしに、この頃、擇善居櫻寧(たくぜんきょえいねい)室主人の著はせる『壽艸(ことぶきぐさ)』及び『養性訣』を一覧せり。その要は、飲食、睡眠、体容、呼吸、心意の五事を調和するに在り。簡にして約なりと云ふべし。
而(しか)してその調和の法を読むに、大いに我が本論の五法(素食法、導引法、灌水法、観念法、吐納法)と互ひに発揮するもの有るを覚ゆ。即ち抄録して以て附論となすも、又摂生の道は実に人生の一大事なれば、その善美共に尽くさむことを希(こいねが)ふの一誠に出ずるのみ。 #0457【無病長生法(1) -総論-】>>
人の病、種々ありと雖(いえど)も、その原因を究むる時は、内より発するものと外より襲へるものとの二つに過ぎず。外より襲ひ来(きた)れる邪気は、譬へば城を囲む敵の如く、内より発し出ずる病気は、譬へば味方の吾に背けるが如し。
それ叛心(はんしん)の者、城中に在りて密かに外敵に内応し、内外力を合せて攻撃せば、如何なる金湯(きんとう)の名城にても決して保たるべきものにあらず。これに反して、城内心を一致して守衛常に厳しく、兵糧・弾薬も乏しからず、援兵よくその任に当たらば、如何なる外敵の押し寄せ来るも、唯(ただ)一戦に逐(お)ひ退けむこと、何の労かあるべき。古への「善く戦ふ者は勝ちやすきに勝つ」と云へるは、病の未だ萌(きざ)さゞるに防ぎ、邪の未だ至らざるに退くるの謂(い)ひなり。これを摂生の大意とす。
凡そ人には孰(いず)れも銘々享け得て定まれる天禄あり。その天禄を勝手に食ひ尽くさず、常に恐れ貯へて、天に預け置くやうに勤むるが人生第一の徳行なり。 #0263【『幽界物語』の研究(33) -寿命について-】>> #0326【『異境備忘録』の研究(11) -「運命」の正体-】>> #0341【『異境備忘録』の研究(26) -神仙感応経-】>>
この徳行を勤め行ふ人は、心を常に倹約に安んじて、常食は必ず薄味にて事足らす故に、偶々(たまたま)美味を食へば、殊(こと)に甘美を覚えて大いに身体の養ひとはなるなり。これに反して常に美味に飽ける者は、その口既に美味に慣れて、美味の美味たる味を感ぜず、他人の目より観れば、定めて満足ならむと思はるれども、本人の心に取りては、その人の一ヶ月の美食は却て倹約者の一日の美味を得るには若(し)かざるなり。
又、家業に身を委(ゆだ)ねて昼夜勉強する人が、偶々一日の清閑を得て、その好める道に心を慰むるは、甚だ愉快を感じて大いに性格の養ひとはなるなり。これに反して常に安逸に耽(ふけ)る者は、その身既に安逸に慣れて、安逸の安逸たる味を感ぜず。他人の目より観れば、定めて安楽ならむと思はるれども、本人の心に取りては、その人の一ヶ月の安逸は却て勉強家の一日の清閑を得るに若かざるなり。
その他、衣服住居百般の事に皆この事あり。心あらむ者はよくよくこの事を決定して、倹約の間に徳行を積み貯ふべし。これを摂生の大体とす。
古人の語に「人怠りて奢(おご)れば貧しく、勤めて倹(つつまや)かなれば富む」と謂(い)ひしは、身を修め家を保つの要法にして、摂生の道も又決して外ならざるなり。如何にとなれば、作業を怠らざれば、体の運化(こなれ)快(よ)く、逸居(いっきょ)せざれば、着過ぎ、飲み過ぎ、食べ過ぎの害無し。諺に曰く、「流水は腐らず戸枢(こすう)蝕まず」と。皆動く故なり。
されば無病にして幸福を祈るには、勤めと倹(つつまし)きとの二つを行ふに若くはなし。この二つを守るには、畏(おそ)ると忍ぶとより善きぞなき。畏るとは天命人事を畏るゝなり。忍ぶとは欲を堪(こら)へるなり。
それ人、酒を過ぎさば身体の害とならむことを畏れてこれを忍び、美味に飽かば胃腸の消化を悪しからむことを畏れてこれを忍び、家業を怠れば家の敗(やぶ)れむことを畏れてこれを忍び、財を費やさば産の傾かむことを畏れてこれを忍び、無理非道を行はゞ世の謗(そし)りを致し人の憤りを来(きた)さむことを畏れてこれを忍び、子孫己が悪行を学ばゞ終には家を亡ぼし祖を辱(はず)かしめむことを畏れてこれを忍び、もしこれ等の畏れを忘るれば体の病身となるのみならず、天の責め、君父の咎め、世間の謗り、皆一身に集ひ来りて、身を損なひ家を亡ぼすに至らむことを返す返すも畏れ忍ぶべし。
さて、この般の欲を忍び堪(こら)へることは、頗(すこぶ)る為し難きことのやうなれども、実際その為し難きは僅かに一週間ほどのことなり。凡そ酒を断ち煙草を断ち、食を節し眠を節し、色を斥(しりぞ)け欲を斥くる等、総て旧憤を脱却するは始めの一週間に在り。十分の忍力を以て立派にこの間を踏み破らば、次の一週間は大いに安く、又その次の一週間は大いに楽なり。
かくしつゝ慣れ来りて、今は常となりし境界を以て往日(おうじつ)を顧み比ぶれば、その安楽愉快なること、実に言はむかた無し。真実の大丈夫はこの道理を決定して自悟し、この実事を断行して自得すべし。これを摂生の大要とす。 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
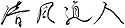
|
|
カテゴリ:無病長生法 |
 |
| |
|
|
| |
| ▼関連記事一覧 |
 |
#00457 2017.1.27
無病長生法(1) -総論-
|
|
(清風道人云、『無病長生法』の著者である川合清丸大人は、因幡国・太一垣神社の神職であった父親の影響もあって幼少から神道を学び、同神社の社掌宮司、更に大神山(おおがみやま)神社の権宮司を務められましたが、京都、大阪、東京等へ遊学した際、日本人の信仰心や道徳心の荒廃した風潮を目の当たりにし、これをきっかけに神道だけでなく儒教、仏教、キリスト教等につ�
|
|
|
カテゴリ:無病長生法 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
#00341 2015.2.26
『異境備忘録』の研究(26) -神仙感応経-
|
|
「羽前国の人にて竹内某とて、玄角大真人の伴になりて神仙界へ安政二(1855)年の頃より出入りする人あり。その人の根元は常に『太上感応篇(だじょうかんのうへん)』を誦読(しょうどく)して、行ひ正直にして父母に孝敬し、神仙を慕ひ願ひ、朝夕空に向ひて『大祓詞(おおはらえのことば)』と『太上感応篇』とを誦して、幽冥に坐(ま)す神仙等とて拝礼する事怠らず、遂に
|
|
|
カテゴリ:『異境備忘録』の研究 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
#00326 2014.11.27
『異境備忘録』の研究(11) -「運命」の正体-
●
|
「小童君が神界にて司命の簿籙(ぼろく)を毎年十月九日より改定し給ふ時は、御頭に金色なる簫(笙)に似たる物を二つ合せたるが如き冠を召し、その中より孔雀の尾、三尾を出し給へり。左の御手に、長さ三尺ばかりの丸木に白玉三十二貫きたる緒の総(ふさ)の付きたるを持ち給ひて、霊鏡台に向ひて座し給へり。」『異境備忘録』
地上人類はもとよりのことですが、顕�
|
|
|
カテゴリ:『異境備忘録』の研究 |
続きを読む>>
|
|
|
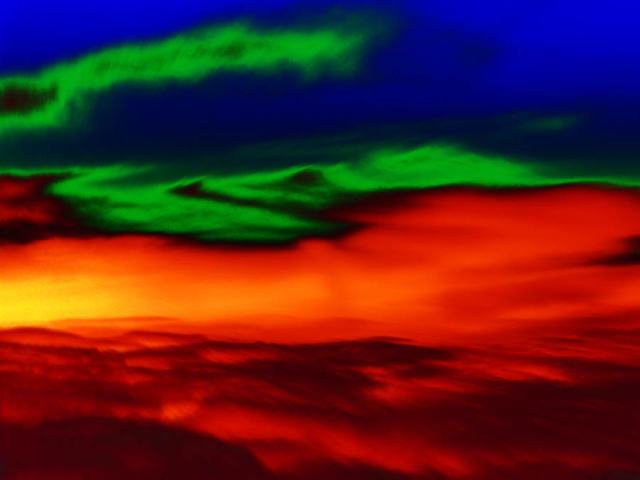
|
|
 |
|
|
 |