| |
| #00101 2011.4.29 |
| 神代第四期のはじまり
|
 |
往古、この地の世界において、造化気運の変遷に伴う幽政上の画期的一大変革が行われました。それは、天孫降臨に先立って行われた幽顕分界(幽界と顕界を完全に分離すること)です。 #0023【この世界だけがすべてではない】>> #0024【幽顕分界という歴史的事実】>>
日本では、天孫降臨以後の御三代(邇邇芸命(ににぎのみこと)、日子穂穂出見命(ひこほほでみのみこと)、鵜葺草葺不合命(うがやふきあえずのみこと))の約2500年を経る間、なお幽顕相通の事実があり、神人雑居のままに推移しましたが、人皇第一代神武天皇の御世に及んで、造化気運の向かうところ遂に神人分居の隔世期(かくせいき)が到来し、それ以来、人の寿命も短縮して今日のような人間の世と一変したことが伝えられています。
幽顕分界とは、地球上の神政を顕幽の両政に分かち、顕事(あらわごと)に属する諸事を天照大御神の神孫邇邇芸命に分任し、幽事(かくりごと)に属する諸事を須佐之男命の神孫大国主神に分任して、顕幽両界に関する分治の原則が定められたことです。 #0062【三貴子の誕生】>> #0072【宇気比の神術】>> #0088【須佐之男命の行方】>>
これを神の側からいえば、人界という一つの独立した界を立ててこれを顕界とし、神や顕界を去った霊の世界を幽界として、明らかに神人分離の制を敷いたということになりますが、このことによって造化の気運もまた変化し、地球上における玄妙霊異の気線も極めて低下したものと考えられます。
神武天皇の時代になって、幽界の一界として山人界(さんじんかい)が創設され、地上霊異の人物の多く(いわゆる縄文人)がこの界へ編入されたことが宮地水位先生によって伝えられていますが、これも幽顕分界の一余波と見るべきでしょう。
何のために幽顕分界が行われたかは、造化大元霊の深き神量(かむはかり)によるものであり、人智で測り知り得るところではなく、ただ太古の地球上にこのような大変革があったということを古伝承によって知識し得るに止まりますが、太陽神界(高天原)の天津神(あまつかみ)である邇邇芸命を地球に降して地界の顕事を治(し)ろしめすこととし、地界の国津神(くにつかみ)である大国主神を昇遷して幽中の神政を治ろしめすこととした天地交流・陰陽交差の玄理を拝する時、青人草(人類)に対して何ごとかを期待される深遠なるご神意を感じます。 #0029【造化大元霊】>> #0095【世界太古伝実話 -大元の神の意志】>>
地上に生を享(う)けて生きとし生けるものは、寿を終えた後、必ず霊魂は幽中に入りますが、既に太古より数十万年を経過し、その数を累計すればどれほどの数とも知れず、天文学的な数に及ぶ帰幽霊の出自進退集散に関する幽中の神政こそは、幽事中でも最大の幽事に属するものであることは間違いないでしょう。 #0010【「死」と呼ばれる現象】>>
この幽事を主宰する神は、よほど大徳霊威でなければ、このような大任を務めることが困難であろうことは想像に難くありませんが、この大任に抜擢され、八百万神を統率して幽政を主宰する大神こそ大国主神です。その大徳は天性の神性もさることながら、数度にわたる生死の関門をさえ潜(くぐ)り、耐え難く忍び難い経験を経ながらも、温厚誠実な信念(神念)を貫き通した至誠貫徹の成果によるものと拝察され、また『古事記』や『日本書記』においても、この大神に関するエピソードは他のどの神に関するよりも多く、わたしたち人間が目指すべき生き方のヒントがそこに示されているように思われます。
「大国主神、またの名(みな)は大穴牟遅神(おおなむちのかみ)と謂(まお)し、またの名は葦原色許男神(あしはらしこおのかみ)と謂し、またの名は八千矛神(やちほこのかみ)と謂し、またの名は宇都志国玉神(うつしくにたまのかみ)と謂す。併せて名五つあり。」『古事記』
大国主神(おおくにぬしのかみ)
このご神名は須佐之男命から賜わったもので、地球上(豊葦原水穂国)の主権の神という意味です。
大穴牟遅神(おおなむちのかみ)
このご神名は「大名持」という意味で、大いなる名を持つ神であるため、このように称します。
葦原色許男神(あしはらしこおのかみ)
これは初めのご神名で、幼名ともいうべきものですが、葦原は地球のこと、色許男とは厳しく勇気ある男神という意味です。
八千矛神(やちほこのかみ)
このご神名は、この神の幸魂(さきみたま)奇魂(くしみたま)が分離して分魂(わけみたま)として活動した際に授けられた広矛(ひろほこ)を突き刺して国(地球)を平定するという意味です。 #0038【一霊四魂】>>
宇都志国玉神(うつしくにたまのかみ)
このご神名は、顕界、つまり顕国(うつしくに)の魂の神という意味で、これも須佐之男命より賜わったものです。
この他にも、大地主神(おおとこぬしのかみ)、大物主神(おおものぬしのかみ)、大国魂神(おおくにたまのかみ)など多くのご神名がありますが、要するにいずれも地球上の主権を司る神という意味の称号です。(大物主というのは物の主という意味ですが、幽界に属する霊物をすべてモノといいます。モノノケ、マガモノなどのモノも同じですが、大物主とはそれらすべての霊物の主として司るという意味です。また大国魂とは、世界各国の国魂(くにたま)を統(す)べる、つまり統率するという意味で、総産土神(そううぶすなしん)ともいえます。) |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
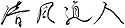
|
|
カテゴリ:日本の神伝 |
 |
| |
|
|
| |
| ▼関連記事一覧 |
 |
#0088 2011.2.24
須佐之男命の行方
●
|
|
「かれ、ここを以てその速須佐之男命、宮造るべき地(ところ)を求(ま)ぎたまひて出雲国に到りまし、須賀の地にて詔(の)りたまはく、「吾(あれ)、この地に来まして、我(あ)が御心すがすがし」とのりたまひて、そこに宮作りて坐(ま)しましき。かれ、その地は今に須賀といふとぞ。この大神、初め須賀宮を作りし時に、その地より雲立ち騰(のぼ)りき。かれ、御歌(�
|
|
|
カテゴリ:日本の神伝 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
#0072 2010.12.15
宇気比の神術
●
|
「日神(ひのかみ)、素盞鳴尊(すさのおのみこと)と共に相対(あいむか)ひて立誓(うけい)て曰(のたま)はく、「もし汝(いまし)心、明浄(あかくきよらか)にて、凌(しの)ぎ奪ふの意(こころ)有らずば、汝(いまし)の生む児(みこ)必ず当(まさ)に男(ひこみこ)ならむ」と言(のたま)ひ訖(お)へて」『日本書紀』
この『日本書紀』の本文は『古事記�
|
|
|
カテゴリ:日本の神伝 |
続きを読む>>
|
|
|
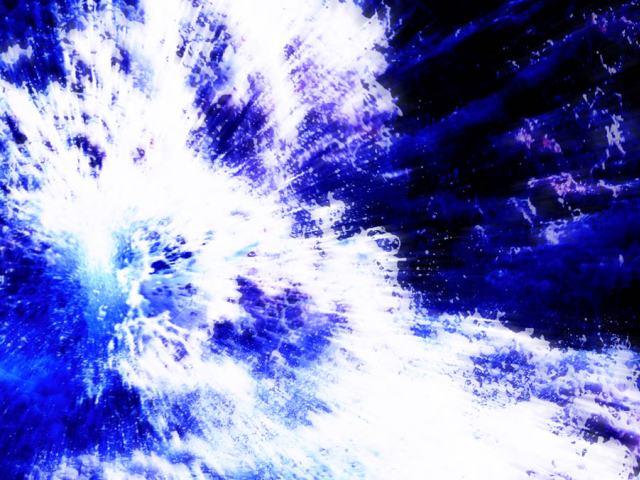
|
|
 |
#0062 2010.10.25
三貴子の誕生
●
|
「ここに左の御目を洗ひ給ふ時に成りませる神の名(みな)は、天照大御神(あまてらすおおみかみ)。次に右の御目を洗ひ給ふ時に成りませる神の名は、月読命(つきよみのみこと)。次に御鼻を洗ひ給ふ時に成りませる神の名は、建速須佐之男命(たけはやすさのおのみこと)。」『古事記』
「この時伊邪那岐命、大(いた)く歓喜(よろこ)びて詔(の)り給はく、「吾(�
|
|
|
カテゴリ:日本の神伝 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
#0023 2010.3.31
この世界だけがすべてではない
|
|
わたしたちが日常生活をおくっているこの世界を、やまとことばで「あらわよ(顕界)」といい、わたしたちの五感で感知できない異次元世界を「かくりよ(幽界)」といいます。そして宮地水位先生の『異境備忘録』に「幽界は八通りに別れたれども、またその八通りより数百の界に別れたり」とあるように、この幽界には、尊い神々の世界をはじめ、神の眷属(けんぞく)の世界�
|
|
|
カテゴリ:玄学の基本 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
#0010 2010.1.20
「死」と呼ばれる現象
●
|
|
日本古学によれば、人は死亡と同時に天国へ昇ったり地獄へ直行したりするものではありません。また、よほどの悪行をはたらいて悪因縁をつくった者とか、恨みや憎しみの念で凝り固まった者、あるいは自殺をはかった者でなければ、死の直前の苦痛というものはほとんど感じないのが普通です。ただ、生前に霊魂の存在とか死後のことなどにまったく無関心だった人は、自分が死�
|
|
|
カテゴリ:玄学の基本 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |