| |
| #00855 2023.09.1 |
| 天地組織之原理(96) -須佐之男命、出雲の地へ-
|
 |
「出雲国の肥の河上に在る鳥髪(とりかみ)の地(ところ)に降りましき。この時、箸(はし)その河より流れ下りき。こゝに須佐之男命、その河上に人有りけりと以為(おも)ほして、尋ね覓(ま)ぎ上り往きましゝかば、老夫(おきな)と老女(おみな)と二人在りて、童女(おとめ)を中に置きて泣くなり。汝等(いましたち)は誰ぞと問ひたまへば、その老夫答言(まお)す、僕(あ)は国神(くにつかみ)、大山津見神(おおやまつみのかみ)の子なり。僕が名は足名椎(あしなづち)、妻(め)が名は手名椎(てなづち)、女(むすめ)が名は櫛名田比売(くしなだひめ)と謂(まお)す。亦、汝が哭(な)く由(ゆえ)は何ぞと問ひたまへば、我(あ)が女は本(もと)より八稚女(やおとめ)在りしを、こゝに高志(こし)の八俣遠呂智(やまたのおろち)、年毎(としごと)に来て喫(くら)ふる、今それ来ぬべき時なるが故に泣くと答白(まお)す。」
こゝに挙げたるは『古事記』本伝の明文なるが、始めに「出雲国の肥の河上に在る鳥髪の地に降りましき」とあるは、前に『日本書紀』の明文を挙げて講じたる「出雲国の簸(ひ)の川上なる鳥上(とりかみ)の峰に到りましき」と同じ伝なるを、『書紀』には「峰」とありて『古事記』には「地」とあり、山上と山下との別ある如く思はるゝを、よく事の順序を考ふるに始め降り坐したるは鳥上峰なるべきを、その時より所々に渡り給ひて樹種などを播生(うえおわ)し給ひ、再び又この所に来給へる順序なれど、『古事記』にはこの次に「故(かれ)、今より天降り坐す」と云ふ伝もあればこの時初めて降り着き給へる如く聞こゆれども、樹種を播生し給へるは必ずこれより前なるべければこゝに多少の錯簡あるべし。尚よく考ふべし。 #0853【天地組織之原理(94) -五十猛神の御功業-】>>
次に「この時、箸その河より流れ下りき」とある「箸」と云ふは、文字によりて考ふれば食事に用ゆる箸の如く聞こゆるを、この時代は未だ地球上に火食の道は開けざる時にて、国津神等に食ありとすれば煮炊きせざる食と見るべきなれば箸は如何あらんと考へらるれども、箸は匙(さじ)の事とも聞こゆればこれ等の物を用ひ給へることありしならんか。
後世の人智を以て考ふる時は最早天地開闢より神代第三期に至り五穀の元種も成りし後なれば、これより前に早く火食の道もあらんと思はるれども、奥津比古・奥津比売神までは青人草にも火食の道あること明文に見えざれば、これまでの青人草に食あるものとすれば、必ず果実或は煮炊きせざる五穀の類と見るの外無し。この時の青人草は皆神仙の如きものなれば、火食は必ず無き理(ことわり)なり。 #0452【『本朝神仙記伝』の研究(70) -足柄山五仙人-】>>
今にても火食を断ち果実のみにて生存する人もある程のことなるに、この時代は彼の支那の伏羲氏・神農氏より遥か以前に当る前世界たる太古のことなれば、未だ火食無しと云ふも疑ふ所あるべからず。 #0530【君子不死之国考(3) -皇孫命降臨の年代-】>>
特にこの次に第四期大国主神の国土経営までは、たとへ五穀の元種はありとも農作の道は非ざる理なるをも考へ合せ、箸の伝は如何なる事と深く考ふべきなり。余(よ)は未だ思ひ定めず。兎に角、人の所持すべき物の流れたるものなるべし。
次の「こゝに須佐之男命、その河上に人有りけりと以為ほして、尋ね覓ぎ上り往きましゝかば、老夫と老女と二人在りて、童女を中に置きて泣くなり。汝等は誰ぞと問ひたまへば、その老夫答言す、僕は国神、大山津見神の子なり」はよく聞こえたれば解を加へず。
次に「僕が名は足名椎、妻が名は手名椎、女が名は櫛名田比売と謂す」とある「足名椎」「手名椎」は先哲の説に、その童女の足を撫で手を撫で愛しみ給ふより名付けたるにて、「足撫豆知(あしなでづち)」「手撫豆知」の約言なりと云はれたり。
「櫛名田比売」とある「櫛」は美称なりとあれども、又「奇霊(くしび)」の「奇」にもあるべし。「名田」は「稲田」とあるべきを、櫛のシの音にイの響きあるが故にイを省きたるなりと本居先哲の説あり。稲田と云ふは地名と聞こゆるなり。
次に「汝が哭く由は何ぞと問ひたまへば、我が女は本より八稚女在りしを、こゝに高志の八俣遠呂智、年毎に来て喫ふる、今それ来ぬべき時なるが故に泣くと答白す」とあるも明文の表は聞こえたる通りにて、「高志」と云ふは地名なり。「遠呂智」と云ふは次に講究すべし。
さてこれまでの本文の意は粗(ほぼ)かくの如きことなるが、これより次々『古事記』の明文を挙げて講述すべきなれども、この伝は特に長き明文なるのみならず、第三期の講述筆記紙数限りあれば大綱略解の例によりて、以下遠呂智平定の伝は表は別に解を加へずともよく聞こえたることなれば、一応明文を朗読したる後、語解等は先哲の説によりて講究すべきものとしてこれを略し、この伝は特に疑点の多かるべき伝なれば、如何なる理由なりと云ふ御疑点に就て御質問あるに随ひ、先哲の説に余が一家説を合せて意見を述ぶべし。 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
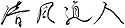
|
|
カテゴリ:天地組織之原理 |
 |
| |
|
|
| |
| ▼関連記事一覧 |
 |
#00853 2023.8.20
天地組織之原理(94) -五十猛神の御功業-
●
|
|
『日本書紀』曰く、「この時素盞鳴尊、その子(みこ)五十猛神(いそたけるのかみ)を師(ひき)ひて新羅国(しらぎのくに)に降到(くだ)りまして、そしもりの処(ところ)にましまして、乃(すなわ)ち興言(ことあげ)して、この地(くに)は吾(あれ)居(お)らまく欲せずと白(の)りたまひて、遂に埴土(はに)を以て舟を作り、乗らして東に渡りまして出雲国の簸(�
|
|
|
カテゴリ:天地組織之原理 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
|
|
 |
#00452 2016.12.28
『本朝神仙記伝』の研究(70) -足柄山五仙人-
●
|
|
足柄山の五仙人は、正覚院(しょうかくいん)と云ひ、満善坊と云ひ、十全院と云ひ、養徳医師と云ふ。今一人はその名を知らず。皆、足柄山に住む仙人なり。孰れもその元何人(なんびと)たりしかを詳らかにせず。唯、養徳医師のみは、江戸日本橋の辺(ほとり)に医業を為したる者なりと云ふ。固(もと)より山中の隠者にして、絶へて知る者無かりしが、猟師・水原文五郎な�
|
|
|
カテゴリ:『本朝神仙記伝』の研究 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |