| |
| #0007 2010.1.3 |
| 潮の干満と生命
|
 |
さらに、潮の干満は人間の肉体に関係があるだけではありません。地球上のあらゆるものにも、その影響は及んでいます。 #0005【わたしたちの肉体は月と同質?】>> #0006【太陽と月と地球の関係】>>
植物でイヌビワ(クワ科イチジク属、イタブ、イタビとも呼ばれる)という木がありますが、この木は枝を折ると、その枝口から乳白色の汁が出るために、俗に「乳の木」とも呼ばれています。この木の枝を折ってみると、潮の込み時には折り取った枝の折口からは少しも汁は出ず、幹の方の折口からは汁が出ます。これに対して潮の引き時には、幹の方の折口からは少しも汁が出ず、逆に折り取った枝の方から汁が出ます。つまり、幹の方から汁が出るのは潮汐が満潮に向かっている時、枝の方から汁が出るのは潮汐が干潮に向かっている時であり、潮の干満とこの木の体液の流動が、ある一定の法則にしたがって密接な関係をもっていることがわかります。
これはこの木に限らず、どの植物でも同じです。この現象は、潮が満ちている時は地球上の水気が上へ上へと昇っており、潮が引いている時には地球上の水気が下へ下へと降っているため、潮の干満にともなって体液の流動が起こるものと考えられます。これらの事実により、潮の干満、つまり月の旋転は、人間の肉体に関係があるだけでなく、地球上のあらゆる一切のものに影響を及ぼしていることが推量されます。
また、火についても不思議なことがあります。現在のように電灯がない時代は、鉱山のトンネル内では火を灯して作業を行っていましたが、トンネルの中で作業をする人たちは、その火の形状によって昼夜の判別をしていました。まず夜明け頃の火は楕円形の形をしていますが、時がたつにつれてしだいに太って丸くなり、真昼になればほとんど円形に近くなります。そしてまた時がたつにつれてしだいに痩せて細長くなり、夕方頃にはまた楕円形となって、夜が更けるにしたがって炎の幅が狭くなり、真夜中つまり午前0時頃になると、さらに細長くなります。
また、タケノコという植物は、夜のあいだにぐんぐん背が伸びて、昼間は周囲が太くなりますが、自然界では他にもこのような事実をたくさん見出せることでしょう。 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
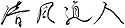
|
|
カテゴリ:玄学の基本 |
 |
| |
|
|
| |
| ▼関連記事一覧 |
 |
#0006 2009.12.29
太陽と月と地球の関係
●
|
ここで、日本古学の見地からみた太陽と地球と月の関係について、簡単に説明しておきたいと思います。
太陽系の成立に関しては、まずビッグバンの後に太陽が結び成され、それから各諸星が細胞分裂のように太陽から分離したという説が伝えられています。つまり太陽と各諸星は母子のような関係にあり(そのため各諸星は太陽のまわりをずっと旋回しています)、太陽の黒点
|
|
|
カテゴリ:玄学の基本 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
|
|
 |