| |
| #00865 2023.10.31 |
| 天地組織之原理(106) -大穴牟遅神、根国に至る-
|
 |
「こゝに亦その御祖命(みおやのみこと)、哭きつゝ求(ま)げば見得て、即ちその木を拆(さ)きて取り出で活かしてその子(みこ)に告言(の)りたまはく、汝(いまし)こゝに有らば遂に八十神の為に滅ぼさへなむとのりたまひて、乃(すなわ)ち木国(きのくに)の大屋毘古神(おおやびこのかみ)の御所(みもと)に遣(や)りたまひき。」
この明文の「こゝに亦その御祖命、哭きつゝ求げば見得て、即ちその木を拆きて取り出で活かして」とあるは別に解を加へずとも聞こえたる通りなり。次に「その子に告言りたまはく、汝こゝに有らば遂に八十神の為に滅ぼさへなむとのりたまひて、乃ち木国の大屋毘古神の御所に遣りたまひき」とあるも明文の表は聞こえたることなるが、この伝は深く講究すべき伝なるにより御参考までに意見を述ぶべし。
まずこの時御祖命、大穴牟遅神をかく木国の大屋毘古神の御許に遣はし給ふは如何なることかと窺ひ奉るに、平田先哲も云はれたる通り大屋毘古神は須佐之男命に常に添ひ給ふ御魂なるによりて、この神の御許に遣はし給ふは御祖命の深き神量(かむはかり)なることを論じ置かれたれば、先哲の説に随ひ尚これを考ふるに、大穴牟遅神はこれまで種々の御大難によりて益々御神徳も高く坐すことなれば、御祖命の御心にもこの神に大地上の大権を得さしめ給はんと思ほしめすべきは素よりのことなるべきを、その御大権は須佐之男命より未だ八島士奴美神(やしまじぬみのかみ)にも御委任無く、八島士奴美神は神代第三期と第四期と造化気運の変遷すべき中間に立ち給ひて、須佐之男命の根国に入り給ひし後はその御手に代りて国土造化の神業を掌り給ふのみなれば、その大権を得さしめ給はんとなれば必ず大祖父・須佐之男大神より伝へ給はざるを得ざる理なるによりて、その大神に添ひ給ふ大屋毘古神木国に坐すが故に、この神の御許に遣はし給へば必ずこの神の深き神量もあるべきとの御心にて、かく御母神の神量なりと窺ひ奉らるゝなり。
この次の『古事記』の伝に「こゝに八十神、求(ま)ぎ追ひ臻(いた)りて矢刺す時に、木の俣より漏(く)き逃(のべ)れて」とあれども、既に前に「その木を拆きて取り出で活かして」とあれば文の適はざるのみならず、「矢刺す時に云々」も聞こえ難き所あり。
先哲はこの「矢刺す時」とある「矢」は始めの氷目矢と違ひ、弓を射て殺さんと弓に矢を刺す時と云ふ意に説かれたれども、その次に「木の俣より漏き逃れて」とある続きたる文の語勢を考ふるに弓矢の事とも聞こえ難く、然りとて氷目矢は始めに打ち立て殺し給ふとあれば、この所には必ず錯簡(さっかん)ある事と窺はるゝなり。
又この次に「御祖命、子に云(の)りたまはく云々」も全く重複の文にして、この所の「こゝに八十神、求ぎ追ひ臻りて」と云ふより「子に云りたまはく」と云ふまでの文字は全く無き方、文語調(ととの)ひてよく聞こゆるが故に、『古事記』の錯簡と見て道理上より暫くこれを省き識者の高論を俟つ。
然る時はこの所の「御祖命、子に云りたまはく」と云ふは、「大屋毘古神、子に云りたまはく」とあるべき文なり。故に平田先哲もこの所は大屋毘古神とあるべきなりと論じ置かれたれば先哲の説に随ひ、次に挙げたる明文には「こゝに大屋毘古神」と云ふ字を補ひ、「子」の字を省きて本講の目的を示す。敢て一家の私見を加ふるに非ず、道理と先哲の説に随ふものなり。
「こゝに大屋毘古神云りたまはく、須佐之男命の坐します根堅洲国(ねのかたすくに)に参向(まい)でよ、必ずその大神議(はか)りたまひなむ。故(かれ)、詔命(みことのり)の随(まにま)に須佐之男命の御所(みもと)に参到(まいいた)りしかば、その女(みむすめ)須勢理比売(すせりひめ)出で見て、目合(まぐ)はひて相婚(みあ)ひまして、還(かえ)り入りてその父に、甚(いと)麗しき神来ましつと白(まお)したまひき。こゝにその大神出で見て、此(こ)は葦原色許男(あしはらしこお)と謂ふ神ぞと告(の)りたまひて」
さてこゝに挙げたる明文に「こゝに大屋毘古神」とあるは、平田先哲の説に随ひ『古事記』本伝の欠文を補ひたるにて、始め「木国の大屋毘古神の御所に遣りたまひき」とある文を受けて必ず「こゝに大屋毘古神云々」と無くては聞こえざるなり。
この大屋毘古神は先哲の委しく論じられたる通り須佐之男命に添ひ給ふ禍津日神の又の御名にして、この時御祖・刺国若比売命よりこの神の御許に大穴牟遅神を遣はし給ふは深き神量なるが故に、大屋毘古神はそれを諾(うべな)ひ大穴牟遅神に告げ給ひて、終に須佐之男命の坐す根堅洲国に参向はしめ給ひしは大屋毘古神の又深き神量にして、大穴牟遅神の神性の他神に異なる神徳坐すを認め給ひ、この神ならば須佐之男命の御神慮に適ひ、必ず神議り給ふことあるべしと根国に参向はしめ給ふ事と窺はるゝなり。 #0817【天地組織之原理(58) -祓戸四柱神の出顕-】>>
次の明文に「その女須勢理比売出で見て、目合はひて相婚ひまして」とある須勢理比売命は須佐之男命の特に御鍾愛に坐す御娘にして、平田先哲も論じ置かれたる通り天照大御神と須佐之男命の御宇気比の時に須佐之男命の御剣を乞ひ給ひて三段に成して天照大御神の吹き成し給ひし三女神を、その物実(ものざね)により詔別(のりわ)け給ひて須佐之男命の御娘なりと大御神の定め置き給ひし比売神なるを、この神の御出顕の時は三度(みたび)に御分体坐して奇成し給ふ神なれども、本(もと)その御物実は御剣の一つなれば後に又三女神御合体の上、根国まで御父・須佐之男命に離れ給はず随ひ給ひて坐すなり。 #0833【天地組織之原理(74) -宇気比の神術-】>>
須佐之男命にも又この御娘は特に御由緒ある御娘なれば、未だこの比売神に御配偶遊ばさるべき高徳の神坐さゞるによりて、かくの如く根国まで御許に離し給はず御鍾愛遊ばされし事と窺はるゝを、この時大穴牟遅神こゝに至り給ひしを須勢理比売命は出で見給ひて、その神の特に勝れたる神なるに愛で給ひて目合ひ坐し、御心の内に御配偶の神と定め給ひしと云ふ意を伝へたるなり。
故に御名の須勢理比売と云ふはこの時御心のソヽリ給ふより名付け奉りし御名にして、須勢理はソヽリの転語なりと先哲の説あり。
次に「還り入りてその父に、甚麗しき神来ましつと白したまひき」とあるは聞こえたる通りにて、この御言詞にても御自ら御心に御配偶の神と定め給ひしこと知られたり。次に「こゝにその大神出で見て、此は葦原色許男と謂ふ神ぞと告りたまひて」とあるは、御娘・須勢理比売命の白し給ふを聞きて須佐之男命御自ら出で見給ひたるに、これは須佐之男命の根国に入り給ふ前に御生まれ遊ばされたる御神孫・葦原色許男神なるが故にかく御名をも予(かね)て知り給ひしなるべし。
さてこれ以下根国の段を悉(ことごと)く明文に挙げて論ずるは略解の及ばざる所なれども、この伝は特に神典中にて疑点多き伝なれば、語解訓解等の委しきことは本居・平田両先哲の伝に譲り、略解の例によりて一応本伝の明文を朗読し、如何なる理由なりと云ふ真理のある所を講究せんが為、御疑点は御質問に随ひ余(よ)が一家の意見を講述すべし。
総て明文の表にてその意のある所を窺ひ難き伝は、初学の為にはその疑点を質問に随ひ講ずるを最も良法とするものなれば、その意を得て御質問を乞ふ。 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
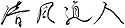
|
|
カテゴリ:天地組織之原理 |
 |
| |
|
|
| |
| ▼関連記事一覧 |
 |
#00833 2023.4.22
天地組織之原理(74) -宇気比の神術-
●
|
『日本書紀』曰く、「こゝに日神(ひのかみ)、素戔嗚尊、共に相対(あいむか)ひ立ちて誓(うけ)ひたまはく、もし汝(いまし)の心、明(あか)く浄(きよら)かにて凌ぎ奪ふの意(こころ)有らずば、汝の所生む児(みこ)必ず当に男(ますらお)ならむ。」
こゝに挙げたる『日本書紀』の明文はよく聞こえたる通り、天照大御神と須佐之男命、相対ひ立ち給ひて大御�
|
|
|
カテゴリ:天地組織之原理 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |
#00817 2022.1.16
天地組織之原理(58) -祓戸四柱神の出顕-
●
|
「こゝに、上つ瀬は瀬速し、下つ瀬は瀬弱しと詔(の)りたまひて、初めて中つ瀬に堕(お)りかづきて滌ぎたまふ時に成りませる神の名(みな)は八十禍津日神(やそまがつひのかみ)、次に大禍津日神(おおまがつひのかみ)。この二神(ふたはしらのかみ)は穢れ繁き国に到りし時、その汗垢(けがれ)に因りて成りませる神なり。」
この伝の明文に「こゝに、上つ瀬は�
|
|
|
カテゴリ:天地組織之原理 |
続きを読む>>
|
|
|

|
|
 |